紅麹サプリ、87%で腎障害続く 摂取中止後も機能低下―阪大
小林製薬の「紅麹(べにこうじ)」配合サプリメントを巡る健康被害問題で、大阪大学の研究グループは7日、日本腎臓学会の会員医師から寄せられた患者192人の調査結果を発表した。腎機能障害が確認された患者のうち、追跡調査した87%で、腎機能の働きが基準値を下回ったままだった。研究グループは「患者の経過を長期に追う必要がある」としている。
調査は2024年3月下旬以降、猪阪善隆・大阪大大学院教授らが実施。学会の会員医師へのアンケートで収集した、4月下旬までに健康被害が報告された患者192人と、うち同年6月上旬まで追跡調査した114人のデータを分析した。
腎臓にある尿細管が傷つき、カリウムやリンなど身体に必要な成分が再吸収されない「ファンコニー症候群」は、追跡調査の時点で患者の多くが改善。一方で、サプリの摂取中止の呼び掛けから約2カ月が経過していたのに、87%は腎機能低下の指標となる数値を下回っていた。血液の老廃物をろ過して尿を作る組織「ネフロン」が減少している可能性があるという。
腎臓の組織を採取する「腎生検」を行った102人では、50%で尿細管間質性腎炎が、32%で尿細管壊死(えし)が認められた。
腎疾患に投与される免疫抑制作用を持つステロイド薬では治療効果が確認できず、研究グループは「免疫異常とは異なるメカニズムで腎臓の機能障害が起きたのではないか」としている。
猪阪教授は「腎機能が低下したままの患者が多く見受けられた。今後改めて調査が必要だ」と話している。
参照元:JIJI.com(2025年1月8日より)
Contents
紅麹サプリ健康被害問題の概要
2024年、小林製薬が販売する紅麹配合サプリメントに関する深刻な健康被害が明らかになりました。
大阪大学の研究グループによると、腎機能障害を訴えた患者192人のうち、追跡調査した114人の87%が腎機能の低下が続いており、基準値を下回る状態が続いています。この問題では、腎臓内の尿細管が傷つき、カリウムやリンなどの体に必要な成分が適切に再吸収されない「ファンコニー症候群」や、尿細管壊死(えし)が多数確認されました。
患者の一部では症状が改善したものの、腎臓の機能低下を指標とする数値は回復しておらず、血液の老廃物をろ過して尿を生成する「ネフロン」の減少が疑われています。さらに、腎疾患治療で一般的に使用されるステロイド薬も効果が見られず、研究者らは免疫異常とは異なる新たなメカニズムが関与している可能性を指摘しています。
このような深刻な健康被害の背景には、商品開発段階でのリスク検証の不足や、製品の安全性に関するモニタリング体制の不備が潜在している可能性があります。研究者たちは「患者の経過を長期にわたって追跡する必要がある」と述べており、同時に企業側の迅速な対応が求められています。
事業者が注意すべき4つのポイント
今回の紅麹サプリメントによる健康被害問題から、サプリメント事業者が製品の安全性や信頼性を確保するために取り組むべき課題が浮き彫りになりました。
以下では、具体的に注意すべき4つのポイントを解説します。
①機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化
食品衛生法施行規則が改正され、令和6年9月1日より、事業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者(届出者等)に限る。)は、以下の内容が義務化されました。
- 機能性表示食品及び特定保健用食品に関する健康被害に関する情報を収集すること(このことに関する衛生管理計画の策定を要する。)
- 上記に関する健康被害の発生や拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等へ提供すること
健康被害情報を知った日から15日以内に情報提供を行う必要があります。
②製品の安全性検証の徹底
事業者が製品を開発・販売する際には、安全性を科学的に検証することが不可欠です。
- 臨床試験と科学的根拠の確立
製品の安全性や有効性を確認するためには、適切な臨床試験の実施が求められます。例えば、特定成分が身体にどのような影響を与えるか、特に長期使用の場合の副作用について慎重に検討する必要があります。 - リスク評価プロセスの導入
製品開発段階で、どのようなリスクが潜在的に存在するのかを洗い出し、それを回避するための対策を講じるべきです。今回の紅麹サプリのケースでは、腎機能障害を引き起こす可能性のある成分に関しての事前評価が不足していた可能性があります。
③販売後のモニタリングと迅速な対応体制の構築
製品が市場に出た後も、消費者の使用状況や健康被害の兆候をモニタリングする体制を整えることが重要です。
- 消費者からのフィードバック収集
顧客サポート窓口やアンケートなどを活用して、消費者が製品使用中に感じた異常や違和感を収集する仕組みを構築しましょう。 - 健康被害の早期発見と対応
万が一健康被害が発生した場合には、速やかにリコールを実施し、行政機関と連携して対応策を講じる必要があります。小林製薬のケースでも、行政指導が行われる前に自主的なリコールが求められたと考えられます。
④透明性の高い情報開示
消費者との信頼関係を築くためには、製品に関する情報を正確かつ分かりやすく開示することが重要です。
- 製品成分の詳細な表示
各成分の含有量や安全性に関するデータを明確に表示することは、消費者が安心して製品を使用するための基盤となります。 - 潜在的なリスクの説明
製品を使用することで発生する可能性のある副作用やリスクについても、しっかりと説明する姿勢が求められます。紅麹サプリの問題では、消費者が製品のリスクを十分に認識していなかった点も指摘されています。
まとめ
紅麹サプリメントの健康被害問題は、健康食品業界が抱える課題を浮き彫りにしました。製品の安全性検証や販売後のモニタリング、トラブル発生時の対応など、事業者が取り組むべき課題は多岐にわたります。
特に、消費者への透明な情報開示や被害者サポートの整備は、企業への信頼を守るために欠かせません。また、業界全体で規制やガイドラインの遵守を徹底し、情報共有を進めることで、再発防止に取り組む必要があります。
健康食品市場が拡大する中、事業者一人ひとりが安全性を最優先に考えることが、消費者の健康を守り、業界の持続可能な発展につながるのです。
このニュースから学んでおきたい知識



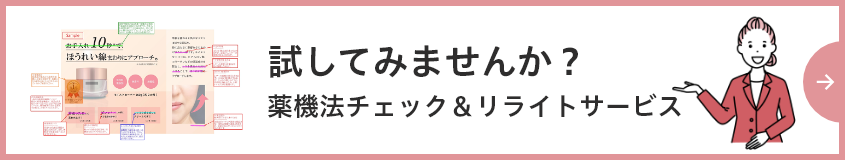


小林製薬の紅麹配合サプリメントを巡る健康被害問題で、大阪大学の研究グループが調査結果を発表しました。
腎機能障害を訴えた192人のうち、追跡調査した114人の87%で腎機能が基準値を下回ったままであることが確認されました。患者の多くは腎臓の尿細管が傷つく「ファンコニー症候群」を発症。改善した患者もいましたが、血液をろ過するネフロンの減少が推測されています。
腎生検の結果、尿細管間質性腎炎や尿細管壊死が多数確認され、従来の治療薬では効果が見られませんでした。研究者らは健康被害の長期的影響を懸念し、引き続き調査を行う必要があるとしています。
本記事では、紅麹問題のような健康被害問題を繰り返さないために事業者が注意すべきポイントについて解説しています。
【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >