Contents
特定商取引法(特商法)とは
インターネットの普及により、商品やサービスの販売形態は多様化し、誰でも簡単にビジネスを始められる時代になりました。しかしその一方で、誤解を招く広告や強引な勧誘、トラブルの多発といった問題も増加しています。
こうした背景の中で、消費者を守り、健全な取引を実現するために設けられたのが「特定商取引法(特商法)」です。
特商法は、特定の取引形態に対して事業者が守るべきルールを定めるもので、違反すれば重いペナルティが科せられる可能性もあります。
本章では、まずその「目的」について詳しく見ていきましょう。
参照元:特定商取引法ガイド
特定商取引法の目的
特定商取引法は、消費者を保護し、公正な取引を確保することを目的として制定された法律です。
とくに、不当な勧誘やトラブルの多い取引形態に対して、事業者側の行動を規制することで、消費者が安心して取引できる環境を整えることが狙いです。
主な目的は以下の通りです。
- 消費者と事業者間の情報格差を是正する
- 消費者が冷静に判断・選択できる環境を提供する
- トラブルや被害の未然防止、及び迅速な解決を促進する
特定商取引法についてはこちらでも詳しく解説しています
特定商取引法の対象となる販売方法
特定商取引法では、特にトラブルが発生しやすい7つの販売方法について、規制が設けられています。これらの取引形態は、消費者との接点が多く、情報の非対称性によって誤解や強引な販売が起こりやすいため、特別に法律で定められているのです。
以下に、それぞれの販売方法の概要を簡単にまとめました。
- 訪問販売
販売員が自宅などを訪問して商品やサービスを販売する形式。強引な勧誘が問題となりやすいため、クーリング・オフ制度が適用されます。 - 通信販売
インターネットやカタログ、テレビショッピングなどを通じて行われる非対面の販売形態。Webサイトでの販売は基本的にここに該当します。 - 電話勧誘販売
事業者が電話で消費者に勧誘し、契約を結ぶ販売方法。意図せぬ契約を防ぐために一定のルールが設けられています。 - 連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法。販売員が新たな販売員を勧誘し、販売網を拡大していく仕組みで、誤解を招きやすいため厳しい規制があります。 - 特定継続的役務提供
一定期間にわたって継続的に提供されるサービス(例:エステ・語学教室・学習塾など)が対象。契約内容の明示義務などが求められます。 - 業務提供誘引販売取引
「簡単に稼げる」などと仕事を提供するように見せかけ、商品購入などを勧める取引。悪質なケースが多いため特に注意が必要です。 - 訪問購入
買取業者が自宅などを訪れ、商品の買い取りを行う方法。消費者が冷静な判断をできるよう、事前説明などが義務付けられています。
これらの取引形態でビジネスを行う場合は、それぞれに応じた法的義務を正しく理解し、適切に対応する必要があります。
特定商取引法には2種類の規制がある
特定商取引法では、消費者を保護し、公正な取引を確保するために「行政規制」と「民事ルール」の2つの側面から事業者の行動を制限・指導しています。
これらはそれぞれ目的や対応方法が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
行政規制
行政規制とは、消費者庁や都道府県が事業者に対して直接的に行う規制のことです。主に悪質な取引を防ぐことを目的としており、以下のような措置があります。
- 業務停止命令や指示処分などの行政処分
- 違反事業者の公表
- 立入検査や報告命令
この行政規制は、あらかじめ設定されたルールを守らない事業者に対して、国が強制力をもって是正を促す手段といえます。
民事ルール
一方、民事ルールは消費者と事業者の間の契約に関するルールです。こちらは、消費者が契約を取り消したり、損害賠償を請求したりすることができる仕組みで、以下のような内容が含まれます。
- クーリング・オフ制度
- 契約の取消し
- 損害賠償請求
民事ルールは、消費者自身が自らの権利を行使するための仕組みであり、法律の知識があるかどうかで対応の幅が変わることもあります。
このように、特定商取引法は「国が取り締まる行政規制」と「消費者自身が守る民事ルール」の2本柱で構成されており、それぞれが連携しながら消費者保護を実現しています。
特定商取引法に基づく表記とは
インターネットを利用した通信販売(ECサイトなど)を行う事業者には、「特定商取引法に基づく表記」を自社のWebサイト上に明示する義務があります。これは、消費者が安心して取引できるよう、事業者情報や販売条件を正確に提示することを目的とした規定です。
この表記が必要になるのは、主に以下のようなケースです。
- インターネットで商品を販売している場合(例:オンラインショップ、個人のネットショップ)
- デジタルコンテンツやサービスを販売する場合
- 定期購入やサブスクリプション形式のサービスを提供している場合 など
つまり、「通信販売」に該当するすべてのビジネスが対象となります。個人事業主や副業レベルの小規模事業者であっても例外ではありません。
これを怠ると、法律違反として罰則の対象になる可能性があるため、必ず適切に記載する必要があります。
表記の項目と書き方
特定商取引法に基づく表記では、消費者にとって重要な取引情報を明示することが求められます。以下の7項目が基本とされており、それぞれの情報を正確かつ分かりやすく記載する必要があります。
① 事業者の氏名等
- 法人の場合:会社名(正式名称)と代表者名
- 個人事業主の場合:個人名(屋号だけでは不可)
株式会社サンプル(代表取締役:山田太郎)
山田花子(屋号:ハナコショップ)
② 事業者の住所、電話番号
- 所在地は番地・建物名まで正確に記載
- 電話番号は連絡が取れる実働の番号を記載(お問い合わせフォームやメールのみでは不十分)
〒123-4567 東京都港区南青山1-2-3 青山ビル5F
TEL:03-1234-5678
③ 商品の販売価格
- 商品ごとに税込価格を明記
- オプションがある場合は追加料金も含めて記載
Tシャツ(Mサイズ):税込2,980円
送料別:全国一律500円
④ 支払い方法と支払いの時期
- 利用可能な支払い方法(クレジットカード、銀行振込、代引き、など)
- 支払いのタイミング(注文時、商品発送前、など)
クレジットカード決済・銀行振込(前払い)・コンビニ払い
支払い期限:ご注文から7日以内
⑤ 商品の引渡時期
- 商品の発送時期や納期を具体的に明記
ご入金確認後、3営業日以内に発送いたします。
⑥ 返品・交換についての規定
- 初期不良時の対応
- お客様都合による返品の可否
- 返品可能な期限、条件など
商品に初期不良があった場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。お客様都合による返品は未使用品に限り、送料はお客様負担となります。
⑦ その他
- 送料、消費税、手数料などが別途かかる場合はその旨を明記
- 販売数量の制限や定期購入の自動更新の有無など、特に注意が必要な点もここに記載
送料は全国一律500円(税込)。代引き手数料:330円(税込)
定期購入は3ヶ月ごとの自動更新となります。
これらの情報は、ECサイトの「特定商取引法に基づく表記」ページやフッターリンクなどで、誰でも簡単に確認できる状態にしておく必要があります。
表記の例(テンプレート)
以下は、実際にWebサイトなどで使える「特定商取引法に基づく表記」のテンプレート例です。必要に応じて各項目を自社の情報に書き換えてご利用ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売業者 | 株式会社サンプル |
| 代表責任者 | 山田 太郎 |
| 所在地 | 〒123-4567 東京都港区南青山1-2-3 青山ビル5F |
| 電話番号 | 03-1234-5678 |
| 電話受付時間 | 平日10:00〜17:00(土日祝を除く) |
| 公開メールアドレス | info@example.com |
| ホームページURL | https://www.sample-shop.jp |
| 販売価格 | 各商品ページをご参照ください(すべて税込表示) |
| 商品代金以外の必要料金 | 送料全国一律500円(税込)、代引き手数料330円(税込) |
| 引き渡し時期 | ご注文から3営業日以内に発送いたします。 |
| お支払方法 | クレジットカード決済、銀行振込、コンビニ払い |
| お支払い期限 | ご注文後7日以内にお支払いください。 |
| 返品・交換・キャンセル等 | 商品に欠陥がある場合を除き、返品・交換はお受けできません。 初期不良の場合は、商品到着後7日以内にご連絡ください。 |
| 返品期限 | 商品到着後7日以内 |
| 返品送料 | 初期不良の場合は当社負担。それ以外はお客様負担となります。 |
※このテンプレートは一例であり、販売する商品やサービスの種類、ビジネスモデルによって必要な記載事項が変わる場合があります。
表記がない場合の罰則
特定商取引法に基づく表記を怠ったり、虚偽の記載をした場合、事業者には厳しい罰則が科せられる可能性があります。これは、消費者の信頼を損なうだけでなく、法的な責任を問われる重大な違反行為です。
以下に、主な罰則内容を詳しく見ていきましょう。
① 指示処分
事業者が特定商取引法の定めに違反していると認められた場合、消費者庁や都道府県知事から「指示処分」が出されることがあります。これは、違反行為の中止や再発防止の措置を命じるもので、是正の勧告に近いです。
もしこの指示に従わない場合、次の「業務停止命令」に進む可能性もあります。
② 業務停止命令
違反の程度が悪質、または指示処分に従わない場合には、業務の全部または一部を一定期間停止するよう命じられることがあります。これが「業務停止命令」です。
3か月間、ECサイトでの商品の販売を停止する命令
この処分を受けると、事実上の営業停止となり、売上への大きな打撃や信用失墜につながります。
③ 刑事罰(罰金・懲役)
特商法第72条では、次のような場合、「100万円以下の罰金」 が科されることが規定されています。
- 著しく事実に相違する表示を行った場合(虚偽の表示、誇大表示など)
- 商品やサービスの内容を実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示をした場合
- 表示義務がある事項を表示しなかった場合(特商法第12条、第36条、第43条、第54条などに該当するケース)
この「表示義務がある事項を表示しなかった場合」というのが、特定商取引法に基づく表記がなかった場合に該当します。
つまり、事業者が特定商取引法に基づく表記をせずに通信販売を行った場合は、原則として、『100万円以下の罰金(第72条)』が科されます。
④ 違反事業者の公表
行政処分を受けた事業者の情報は、消費者庁や各都道府県の公式サイトで公表されます。
- 会社名・代表者名
- 違反内容
- 処分内容(指示、業務停止など)
このような公表は、企業イメージの大幅な低下や顧客離れを招く恐れがあり、長期的な経営リスクに繋がります。
このように、「特定商取引法に基づく表記」を正しく掲載しないことは、ただのミスでは済まされません。事業の信頼性を守るためにも、法令遵守は最優先事項といえるでしょう。
まとめ
今回は、「特定商取引法に基づく表記」について、その背景や必要な項目、違反時の罰則などを詳しく解説してきました。
特定商取引法(特商法)は、消費者を守り、健全な取引を実現するために定められた法律です。とくにインターネット上での通信販売を行う場合、事業者はこの法律に基づいて、以下のような義務を果たす必要があります。
- 販売形態に応じた規制(通信販売、訪問販売、電話勧誘など)
- 「行政規制」と「民事ルール」の両面からの法的対応
- 特定商取引法に基づく表記の明示と、正確な情報提供
違反すれば、業務停止命令や刑事罰、違反事業者としての公表など、事業運営に大きなリスクが発生します。一方で、表記をしっかり整えておくことで、消費者からの信頼を得ることができ、ブランディングや売上向上にもつながります。
オンラインビジネスに関わるすべての方は、特定商取引法の理解と遵守を「最低限のルール」としてしっかり押さえておきましょう。
この記事から学んでおきたい関連知識


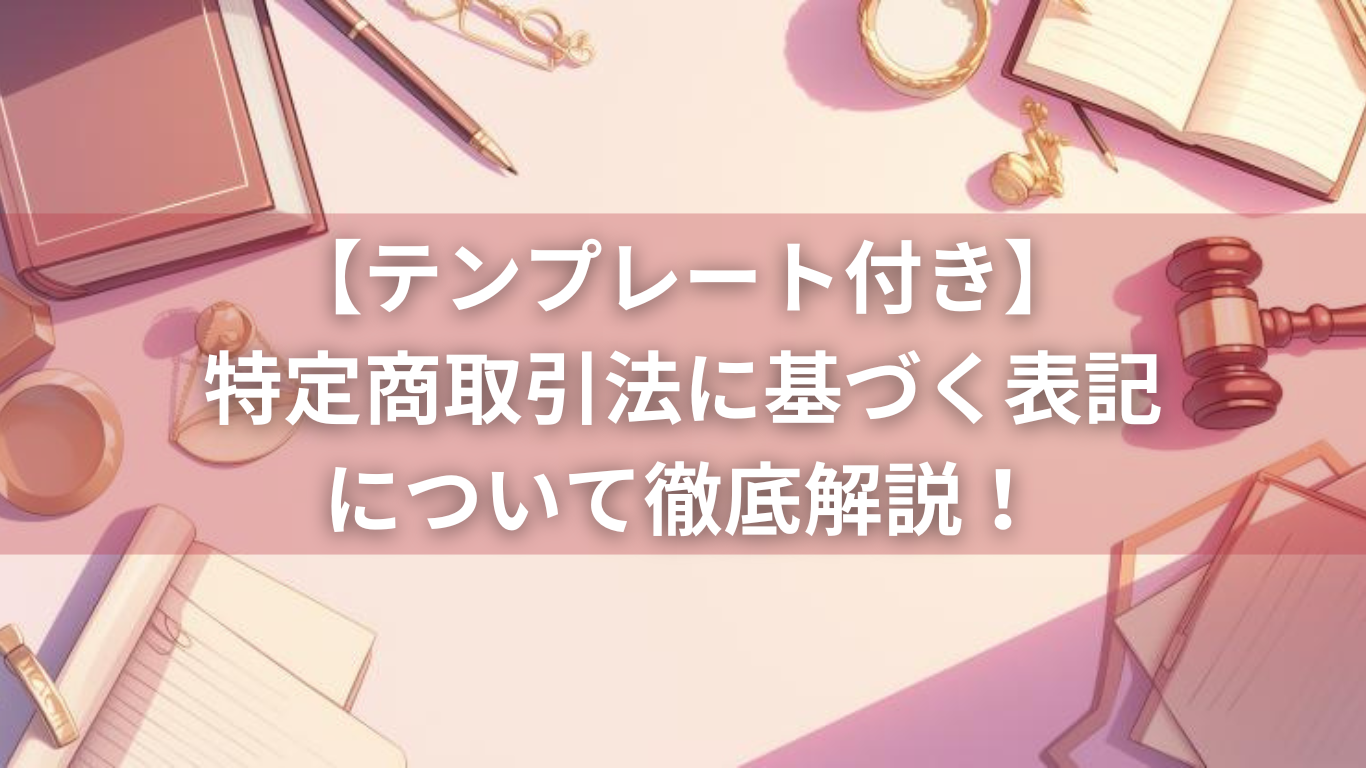
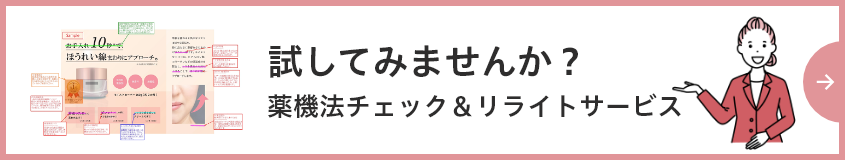


インターネットでの物販やサービス提供が一般化した今、オンラインショップやECサイトを運営するにあたり、「特定商取引法に基づく表記」は欠かせない要素となっています。この表記は単なる義務ではなく、購入者に安心感を与え、信頼を構築するためにも重要なポイントです。
しかし、「どのような項目を記載すればよいのか?」「違反するとどうなるのか?」など、具体的な内容を理解していない事業者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、特定商取引法の概要から、表記内容の具体例、違反時の罰則までを徹底的に解説していきます。これからネットビジネスを始める方はもちろん、既にECサイトを運営している方にも必見の内容です。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >