Contents
変更点①:配合目的は「客観的な実証」が必須に!
まず最も大きな変更点の一つがこちら。
▶ 特記した成分の配合目的は化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、客観的に実証されていること
これまでも「配合目的は化粧品について効能効果の表現の範囲であって事実であること。」とされていましたが、今回はそれがより具体的に明文化されました。
例えば、
- ごくわずかでも配合されていれば「保湿成分」「整肌成分」などと表示していたケース
今後は、配合目的に基づいた効能効果や製剤技術が、客観的に証明されていなければNGとなる可能性があります。
▶ Q&Aでは「自社データ」も可とされているが…
厚労省のQ&A(Q11)では、自社データでも客観性が担保されていればOKとされていますが、広告を作成する際には、必ず製造販売業者に確認することが重要です。
変更点②:デザイン・写真での成分表示にもルールが!
次に重要な変更点がこちら。
▶ 特定成分を写真やデザイン(英文等の表示も含む)で表現している場合、「○○(成分名)△△(配合目的)」のように配合目的と成分名の記載が必須
デザインで成分を強調する場合でも、その配合目的が明確で、かつ客観的に実証されている必要があります。
つまり、写真や英文で「アロエのイメージ」「ヒアルロン酸の分子構造」などを使っている場合でも、
「成分名は?」「どんな目的?」「その根拠は?」
と、当局から指摘を受ける可能性があります。
表示の方法にも新ルールが追加!
これまでは「特記表示は成分名の前または後に」とされていましたが、新たに以下のルールが加わりました。
▶ 「植物成分」「海藻エキス」などの統括的成分
旧Q15では、「植物成分」「動物成分」などは配合目的の記載を省略可能とされていましたが、今回削除されました。今後は、統括的表現であっても、成分名と配合目的を明記する必要があるということを意味します。
▶「アミノ酸系シャンプー」などのカテゴリ表記
旧Q13では「アミノ酸系シャンプー」といった表現は許可されていましたが、今回の通知では削除されています。これは配合成分の特記ではなく商品カテゴリーを述べているにすぎないため、そもそも特記表示のルールとは関係ありません。従って、従来通り配合目的の記載は不要です。
ビタミン表示も緩和? でも要注意!
旧Q18では、「ビタミンA、Dが肌荒れを防ぐ」などの表現は禁止されていました。
しかし、今回の通知では…
「肌あれを防ぐ成分 ビタミンA・Eを配合」は一律NGとはされず、広告全体での誤認の可能性を見て判断されることになりました。
つまり、
- 有効成分であるかのような誤認を与えないか
- 記載された配合目的が、客観的に実証されているか
が判断のポイントとなります。
まとめ:広告作成時は“エビデンス”が鍵!
今回の通知により、化粧品広告での特定成分の訴求は、より厳格なルールのもとで行う必要があります。
とくにポイントとなるのは以下の3つ。
- 配合目的は、客観的に実証されたデータに基づくこと
- 写真・デザイン・英文等での成分表示にも、成分名と配合目的を明記
- 広告全体での誤認表現がないよう細心の注意を払う
今後の広告・販促制作においては、製造販売業者との連携と、根拠資料の確認が不可欠です。
その他の詳細は、各都道府県のHP等で最新情報をご確認ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/yakuji/topic/documents/20250310_1.pdf
この記事から学んでおきたい関連知識


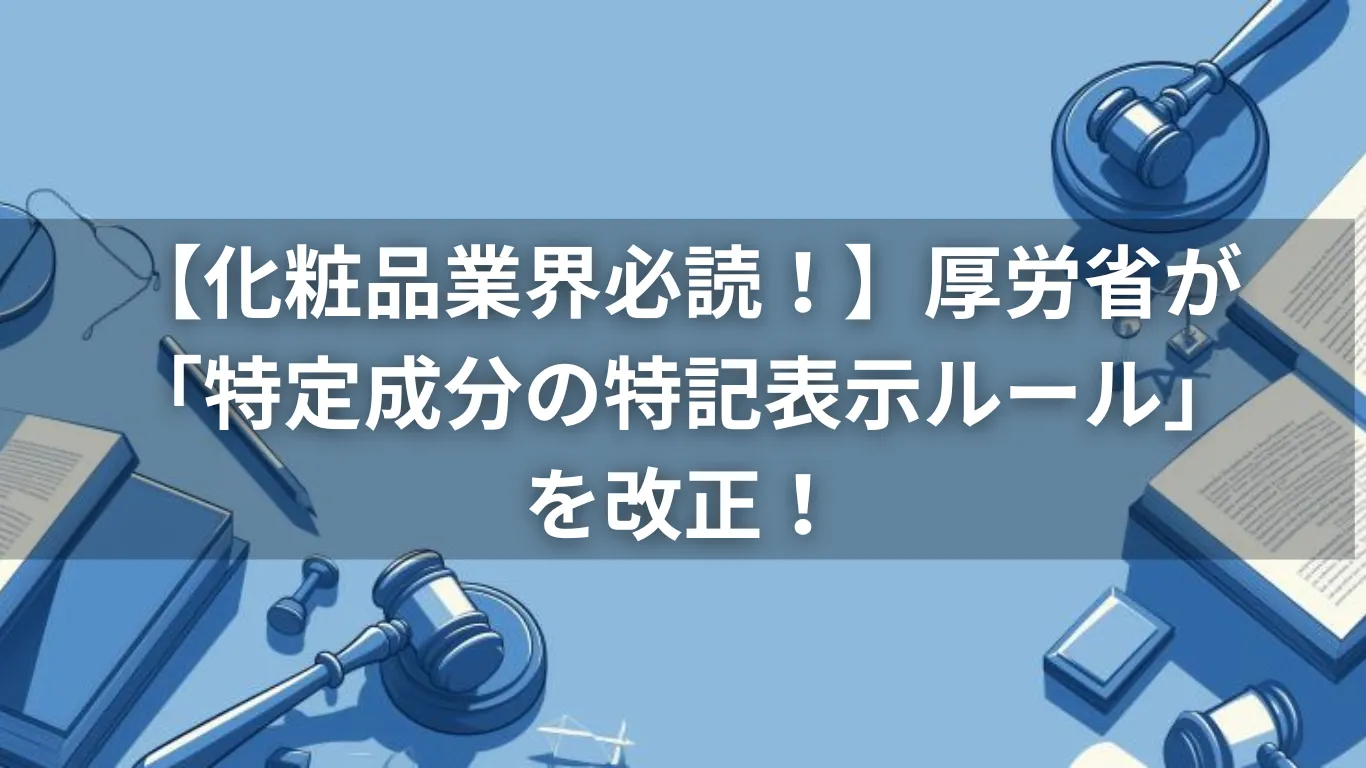
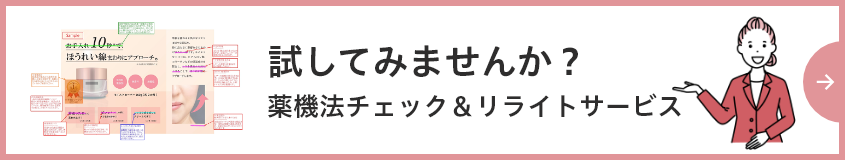


厚生労働省より、化粧品業界にとって非常に重要な以下の通知が発出されました。
『化粧品における特定成分の特記表示について(令和7年3月)』
本通知は、昭和60年に発出された旧通知(薬監第53号)を廃止し、特記表示のルールに大幅な変更を加えるものです。
化粧品の広告・販促表現に関わるすべての関係者にとって、今後の運用を大きく左右する重要な内容となっています。
今回は、そのポイントをわかりやすくまとめました。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >