Contents
景品表示法とは
消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招かないよう、不当な広告や表示を規制する法律を「景品表示法」と言います。
主に、実際の品質よりも著しく優れていると誤認させる「優良誤認表示」や、取引条件が実際より有利であると誤解させる「有利誤認表示」などが禁止されています。
違反が認められた場合、企業には措置命令や課徴金納付命令が命じられることがあります。
景品表示法の目的
景品表示法の主な目的は、消費者が正しい情報に基づいて商品やサービスを選択できるようにするとともに、事業者間の公正な競争環境を確保することにあります。
誇大広告や不当表示が行われると、消費者は誤解し不利益を被る恐れがあり、結果として市場への信頼も損なわれます。
また、不正な広告が横行すると、誠実に営業している企業が競争上の不利を被るため、公平な市場全体の公正性が失われます。
景表法はこうした状況を防ぐために、不当表示を規制し、消費者の利益と市場の健全性を守る役割を担っています。
景品表示法の対象
景品表示法の対象となるのは、商品やサービスに関する広告や表示です。
具体的には、通販サイトやECモールの商品ページ、メールマガジン、パッケージ、チラシ、テレビCM、SNS広告など、消費者が購入を判断をする際に参考にするすべての情報媒体が含まれます。
表示の手段や媒体を問わず、実際の品質・価格・条件と異なる誤解を招く表現であれば景品表示法の規制の対象となります。また、過大な景品の提供によって消費者を不当に誘引する行為も規制の対象の範囲に含まれます。
景品表示法における課徴金制度とは
ここでは、景品表示法における課徴金制度について説明します。
課徴金制度とは?罰金との違い
課徴金制度は、不当表示によって企業が得た経済的利益を回収することを目的とした制度であり、違反の抑止と制裁を目的とする「罰金」とは異なります。
課徴金は違反表示(優良誤認・有利誤認)によって得られた対象商品の売上額の3%を基準に算定され、刑事罰ではなく行政上の措置として科されます。
一方、罰金は刑罰の一種であり、違反行為に対する制裁として裁判所から命じられるものです。課徴金制度は、不当表示による公正な市場競争を維持するための重要な行政手段として位置づけられています。
課徴金の対象となる不当表示
景品表示法で禁止されている不当表示のうち、課徴金の対象となるものは特に消費者に誤解を与える可能性が高い表示です。
主に、実際よりも品質が良いと見せかける優良誤認表示、価格や取引条件を実際より有利であると誤解させる有利誤認表示が該当します。
これらの不当表示によって得た売上額に対し、課徴金が算定・賦課される仕組みとなっています。
優良誤認表示とは
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・規格・性能などを、実際よりも優れているように見せかける不当表示のことです。
このような表示は消費者に誤認を与え、適切な購買判断ができなくなる恐れがあります。
- 果実ミックスジュースの場合
実際にはメロン果汁はほとんど入っていないにもかかわらず、あたかも大部分がメロン果汁であるかのように表示。
- コンサートの座席の場合
実際には、SS席を購入してもアリーナ席にならない場合があるにもかかわらず、あたかもSS席を購入すればアリーナ席であるかのように表示。
このような表示が確認されると、企業には課徴金が科される可能性があります。
有利誤認表示とは
有利誤認表示とは、商品やサービスの価格や取引条件について、実際よりも消費者にとって有利であるかのように見せかける不当表示のことです。
- 携帯電話の通信料金の場合
実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社が最も安い!」と表示。
- 商品の内容量の場合
実際には、他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示。
このように、「これはお得だ!」と消費者に思わせておきながら、実際にはそうでない表示は、消費者の正しい判断を妨げるため、景品表示法違反となり、課徴金の対象となる可能性があります。
参照元:消費者庁
課徴金納付命令が発令されるまでの流れ
課徴金納付命令は以下のような流れで発令されます。
- 消費者庁が事業者に対して調査を実施
- 不当表示が確認されると企業に対して措置命令が発令
- 課徴金の対象となる場合は、消費者庁が違反行為によって得られた売上額を基に課徴金を算定
- 企業に意見提出(弁明)の機会が与えられる
- 不十分となった場合に、課徴金納付命令が発令
課徴金納付命令が発令された場合、指定された期限内に課徴金を納付しなければなりません。
課徴金が科されないケースがある
景品表示法では、本来、不当な表示をした事業者には課徴金が科されますが、例外的に課徴金が科されないケースがあります。
- 表示が不当表示(優良誤認や有利誤認)にあたることを、事業者が知らなかったこと
- その「知らなかったこと」について、注意を怠ったとはいえない=「きちんと確認・注意していた」と認められること
以上の2つの条件を両方とも満たす場合、消費者庁は課徴金を命じることができません(法律第8条第1項ただし書)。
※「知らなかった」という理由だけでは課徴金の免除は認められません。
十分な注意義務を果たしていたにもかかわらず、違反に気づけなかった場合に限り、課徴金の対象外となる可能性があります。
つまり、表示内容の確認や調査を適切に行っていたことが客観的に認められる必要があります。
課徴金の計算方法
課徴金の額は、不当表示によって得られた売上額の3%を基準に算定されます。
対象となる売上額は、違反が行われた期間(原則として最長3年間)における該当商品の総売上です。ただし、以下の場合は課徴金の計算から除外されます。
- 消費者がすでに返品・返金を受けた売上
- 違反表示がなかった場合でも得られたと考えられる売上(例:ブランド力や他の要因で通常通り売れた分)
課徴金の減額について
景品表示法では、違反に対して課徴金が科されますが、一定の条件を満たことで減額や免除が認められる制度(法第10条・第11条)があります。これは企業の自主的な是正や、消費者の被害回復を促すための仕組みになります。
■第10条:自主申告
企業が消費者庁の調査が始まる前に、自主的に違反を申告し、再発防止策を講じた場合には、課徴金が減額または免除されることがあります。
■第11条:返金措置
不当表示によって取引した消費者に対し、購入額の3%以上の返金を行った場合には、その売上は課徴金の算定対象から除外されます。
行政処分を免れる確約手続とは
確約手続とは、企業が景品表示法違反を認めた上で、適切な再発防止策を講じることで、措置命令などの行政処分を受けずに済む制度です。
企業は自主的に確約計画を策定し、消費者庁の承認を得る必要があります。
承認されると、措置命令を受けずに済むだけでなく、課徴金が減額される場合もあります。
ただし、確約内容を守らなかった場合は、改めて措置命令が出されるなど、厳しい対応が取られる可能性があります。
確約手続の目的と概要
確約手続の目的は、企業が自主的に景品表示法違反を是正し、再発防止策を講じることで、公正な市場を迅速に回復することです。
手続きの流れとしては、企業が違反を認めた上で具体的な再発防止策をまとめた「確約計画」を消費者庁に提出し、承認を受ける必要があります。
承認後は確約内容を誠実に履行し、定期的に進捗を報告しなければなりません。
確約計画の必要性と内容
確約手続を利用するには、「確約計画」の提出が必須です。
確約計画とは、企業が景品表示法違反を認めた上で、再発防止に向けた具体的な対応策をまとめた文書のことを指します。
- 違反行為の具体的な内容
- 再発防止策(例:社員教育・広告表示の審査体制の強化など)
- 計画の実施スケジュール
- 進捗報告の方法
消費者庁の承認を得ることで、措置命令などの行政処分を回避でき、さらに課徴金の減額(最大50%)が可能となります。
確約手続が適用される条件
確約手続が適用されるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 景品表示法違反(例:優良誤認表示・有利誤認表示など)が認められていること
- 企業が自主的に違反を認め、「確約計画」を策定すること
- 「確約計画」に具体的な再発防止策が盛り込まれていること(例:社員教育、広告表示の審査体制の強化など)
- 策定した「確約計画」について、消費者庁の審査と承認を受けること
また、承認後は計画を確実に実行し、定められた方法で進捗状況を報告する義務があります。
確約手続が対象外になるケース
確約手続は、本来「企業が違反を認めてすぐに改善するなら、行政処分を回避できる機会」です。
「すぐに反省して改善しようとする企業」を支援する仕組みなので、繰り返し違反したり、最初から悪意がある場合は対象にしないというルールになります。
以下のような悪質なケースは対象外となります。
- 過去10年以内に景品表示法で処分を受けたことがある場合
消費者庁が今回の調査を始めた日などからさかのぼって10年以内に、過去に違反が確定して行政処分を受けている場合は「繰り返し違反している」とみなされ、確約手続は使えません。 - 悪質で重大な違反の場合
企業が、最初から広告表示に根拠がないことを知っていながら、わざと虚偽の広告を出したようなケース。
このように確信的に嘘をついていた場合は、早期の是正は期待できないとされ、やはり確約手続は使えません。
まとめ
課徴金命令が出されると、企業の信用や経済的にも大きな影響を与える可能性があります。
確約手続を活用すれば措置命令の回避や課徴金の減額も可能ですが、そもそも違反を起こさないことが最も重要です。
日頃から広告表示の内容を丁寧に確認し、社内のチェック体制や社員教育を徹底することで、リスクを未然に防ぎましょう。
この記事から学んでおきたい関連知識


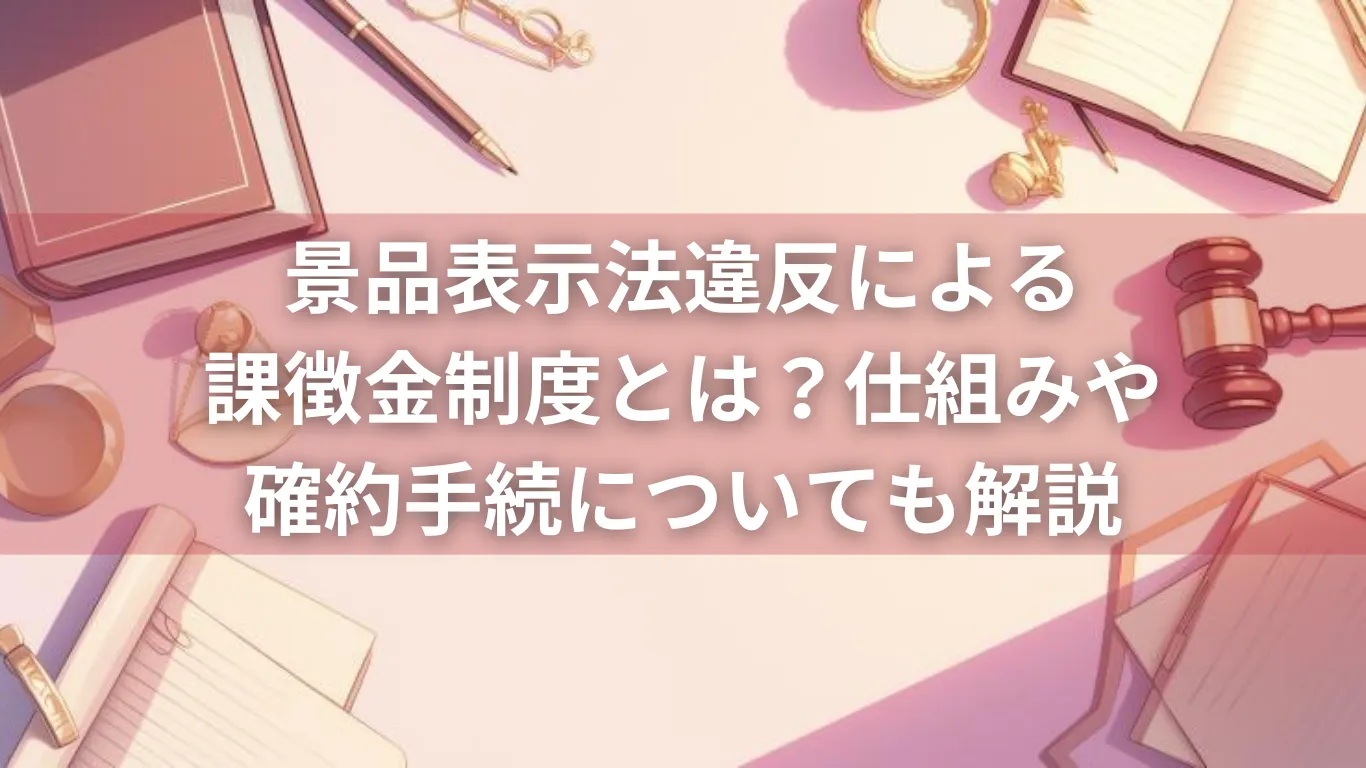
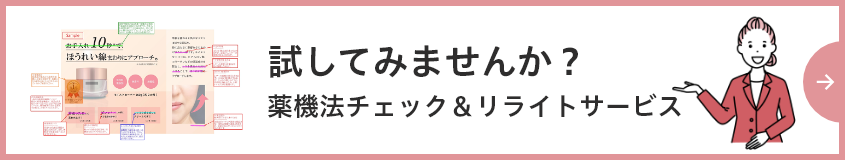


景品表示法違反に対して導入された課徴金制度は、不当な表示による不正な利益を回収し、公正な取引を確保することを目的とした制度です。
この制度は、2013年頃に百貨店やホテルなどで相次いで発覚した食品偽装やメニューの虚偽表示問題を受け、消費者の信頼の回復と再発防止の必要性から導入が検討されました。
また、従来の罰金(上限300万円)では抑止力が不十分と指摘されたことも後押しとなり、2014年の景品表示法改正を経て、2016年4月に課徴金制度が施行されました。
違反後、企業が確約手続を通じて自主的に違反を認め、再発防止策を講じた場合には、措置命令を回避したり、課徴金が最大50%まで減額されることもあります。
さらに、2023年の法改正では、制度の強化や罰則の拡充が図られ、より実効性のある仕組みへと進化しています。
本記事では、課徴金制度の仕組みと事業者が取り組むべき対応策をわかりやすく解説します。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >