Contents
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法(特商法)とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)など、事業者と消費者との間でトラブルが起きやすい特定の取引形態を対象として定められた法律です。
この法律は、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防ぎ、消費者の利益を守ることを目的としています。また、事業者が守るべきルールを明確にすることで、公正かつ健全な市場環境の実現も目指しています。消費者保護と取引の適正化を両立させる、重要な法律です。
表示義務、不当な勧誘行為の禁止、クーリング・オフ制度など具体的なルールが定められています。
参照元:特定商取引法ガイド
特商法の規制の対象となる取引
消費者との間でトラブルが起きやすい、次の7つの取引形態(以下)が特商法の対象となります。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
これらに共通するのは、消費者が十分な情報を得にくく、不意打ちや誤解を招きやすい販売方法が使われる点です。そのため、法律によって取引方法や勧誘行為に対して厳しいルールが設けられています。
以下で詳しく解説します。
①訪問販売
訪問販売とは、事業者が消費者の自宅などを訪れて、商品やサービスの契約を勧める販売方法のことを指します。
道で声をかけて店に連れて行く「キャッチセールス」や、事前に電話などで約束を取りつけて訪問する「アポイントメントセールス」も含まれます。
消費者の自宅等にセールスマンが訪問してリフォーム工事の飛び込み営業をし、契約を行う販売など
②通信販売
通信販売とは、インターネットやカタログ、テレビ、新聞などを通じて商品やサービスを販売する方法です。注文は郵送や電話、インターネットなどで行います。
通信販売では、クーリング・オフ制度は原則として適用されませんが、商品情報や事業者情報などを正しく表示するルールがあります。
ECサイトでのネットショッピング、定期購入、テレビショッピング、カタログ通販など
③電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をかけて商品やサービスの購入を勧め、契約の申し込みを受ける取引のことを指します。
電話を切った後で、消費者がハガキや電話等によって申し込みをしても、この取引に該当します。
「当社の教材で勉強し資格試験に合格すれば在宅でパソコン入力の仕事が出来る」と言って教材を買わせるなど
④連鎖販売取引(マルチ商法)
連鎖販売取引とは、個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)や役務の取引です。
「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、友達を誘ってその人に売れば儲かります」など
⑤特定継続的役務提供
特定継続的役務提供とは、長期間にわたってサービスを提供し、その見返りとして高額な料金を支払う契約のことを指します。
現在は、エステティックサロンや美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室など、特定の7種類のサービスが対象とされています。
⑥業務提供誘引販売取引
業務提供誘引販売取引とは、「仕事を紹介するので収入が得られる」と持ちかけて消費者を誘い、その仕事に必要だとして商品などを買わせ、費用を負担させる販売方法のことです。
「この健康寝具を購入し、モニターとして使用感を報告すれば報酬を得られる」として、商品を購入させる。
⑦訪問購入
訪問購入とは、事業者が消費者の自宅などを訪問し、消費者が所有する物品を買い取る取引のことを指します。
事業者が消費者の自宅に来て「使ってない時計を買い取らせてください」と持ち掛けるなど
特定商取引法で定められている規則
特商法では、消費者との間でトラブルが起きやすい取引において、公正な取引を確保し、消費者を保護するための具体的な規則が設けられています。
これらの規則は大きく分けて、「行政規制」と「民事ルール」の2つに分類され、事業者が守るべき行動や、消費者がトラブル時に利用できる救済手段が明確に定められています。
行政規制
行政規制とは、消費者とのトラブルを防ぐために、事業者に対して定められているルールのことです。
たとえば、契約前に必要な情報をきちんと伝える義務(情報提供義務)や、誇大な広告・強引な勧誘を禁止する決まりなどがあります。
これらに違反すると、消費者庁などから業務改善の「指示」や「業務停止命令」などの行政処分を受ける可能性があります。また、悪質な場合は、罰則の対象になることもあります。
以下で、それぞれの規制ルールについて解説します。
①事業者の氏名や住所、電話番号等の表示
事業者が消費者に対して勧誘を始める前には、次の3つを明確に伝える必要があります。
- 事業者の氏名または会社名
- 勧誘を目的としていること
- 勧誘する商品やサービスの内容
※通信販売と特定継続的役務提供を除く全ての取引類型に適用されます。
事業者が消費者の自宅を訪問し、会社名を名乗らずに「排水管の洗浄をしています。料金は3000円でになります」とだけ説明して勧誘する場合、明示義務違反となります。
②不当な勧誘行為の禁止
特商法では、事業者が消費者に対して、うその説明をしたり、大事なことをわざと伝えなかったりすることを禁止しています。
たとえば、実際よりも安く見せるような価格のごまかしや、分割払いの総額を説明しないといった行為がこれにあたります。
また、強い口調で契約を迫ったり、不安をあおって混乱させたりするような、威圧的な勧誘行為も禁止されています。
③広告規制
特商法では、事業者が広告を出すときに、料金や契約条件などの大事な情報をきちんと表示することが義務付けられています。
また、事実と違う内容(虚偽)や、実際よりも良く見せるような誇大な表現を使った広告は禁止されています。
④書面交付義務
特商法では、契約を結ぶときなどに、料金や契約内容などの重要な情報を記載した書類を、事業者が消費者に渡すことが義務づけられています。
これにより、消費者は後から内容を確認でき、トラブルの防止につながります。
民事ルール
民事ルールとは、消費者が契約後にトラブルに遭った場合や、冷静な判断ができないまま契約してしまった場合に、契約を取消したり解除したりできる仕組みのことです。
代表的なものが「クーリング・オフ制度」で、一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除できます。消費者が自分を守るための、大切な制度です。
①クーリング・オフ制度
特商法では、「クーリング・オフ」という制度が認められています。
これは、契約を申し込んだり、契約を結んだあとでも、法律によって決められた書面(申込書面または契約書面)を受け取ってから、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。
期間は取引の種類によって異なり、次のように定められています。
- 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入:書面を受け取ってから8日以内
- 連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法など):書面を受け取ってから20日以内
なお、通信販売には法律上でのクーリング・オフ制度の適用はありませんが、返品の可否や条件についての特約があれば適用されます。
特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品することが可能です。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があるため、商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。
②意思表示の取消し
特商法では、事業者がうその説明(不実告知)や、わざと重要なことを伝えなかった場合(故意の不告知)に、その説明を信じて契約をしてしまった消費者は、その意思表示を取り消すことができると定められています。
つまり、消費者が正しい判断をできなかった原因が事業者にある場合には、契約をなかったことにできる制度です。
訪問販売で事業者が「このままだと雨漏りの危険があります。今なら特別価格の10万円で修理できます」と勧説明。しかし実際の適正価価格は5万円ほどで特別価格でも何でもなかった。
このように価格について事実と異なる説明(不実告知)を信じて契約した場合には、消費者はその契約の意思表示を取り消せる可能性があります。
③損害賠償等の額の制限
特商法では、消費者が契約を途中でやめる(中途解約する)場合などに、事業者が請求できる損害賠償や違約金の金額には、法律で上限が設定されています。
これにより、事業者が不当に高額な違約金や解約料を請求することを防ぎ、消費者の負担が不当に重くならないよう保護しています。
特商法に違反した場合の罰則
事業者が特商法に違反した場合、まずは消費者庁や都道府県の担当部局が調査を行い、違反が確認されると「指示」や「業務停止命令」などの行政処分が科されます。
さらに、悪質な違反と判断された場合には、刑事告発され、罰金や懲役などの刑事罰が科されることもあります。
違反内容が公表されれば、企業の社会的信用を大きく損なうリスクもあります。
行政処分の種類
特商法に違反した事業者に対しては、以下のような行政処分が行われることがあります。処分の内容は、違反の内容や悪質性に応じて段階的に行われます。
- 業務の改善指示
- 業務停止命令
- 名称等の公表
以下でそれぞれについて解説します。
①業務の改善指示
消費者庁や都道府県の担当部局が、違反行為をやめるよう「業務改善の指示」を出します。
初期の段階で用いられることが多く、比較的軽い処分です。
「誇大広告をやめること」「書面交付を適切に行うこと」などの具体的な改善命令
②業務停止命令
違反の程度が重い、または指示に従わなかった場合に、一定期間の営業活動を停止させる命令になります。
3ヶ月間、訪問販売業務の一切を停止させるなど
また、違反行為に関与した法人の役員や営業担当者に対して、その業務に一定期間従事できなくする命令が出されることもあります。これは再犯防止や組織的違反への対策として用いられます。
代表取締役が1年間、訪問販売業務に関与できないなど
③名称等の公表
行政処分を受けた事業者の社名・違反内容が公表されます。インターネット上にも掲載されるため、企業の信用に大きな影響を与えることがあります。
刑事罰の種類について
特商法に違反すると、行政処分に加え、刑事罰が科されることがあります。法人に対しては、さらに重い罰金が科されることもあります。
①業務停止命令違反に対する罰則
2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方(懲役+罰金)が科されます。
業務停止命令中にもかかわらず、訪問販売をつづけた場合など
【法人も対象となった場合】
a.誇大広告・虚偽表示など(第70条第3号):3億円以下の罰金刑
b.不実告知・威迫・書面交付など(第70条第1号および第2号):1億円以下の罰金刑
c.業務停止命令違反など(第71条から第73条):各条文で決められた額
②不実告知や威迫行為などへの罰則
以下のような悪質な勧誘行為に対しても、懲役または罰金刑が科される可能性があります。
- 不実告知(うその説明)
- 故意の不告知(わざと重要事項を隠す)
- 威迫・困惑行為(消費者を脅す・追い詰める)
- 書面不交付
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(法人が対象の場合は1億円以下の罰金)※特定商取引法 第70条
③名称等の不使用や虚偽表示に関する罰則
- 虚偽の広告を出す
- 名称や所在地などを偽って表示する
これらも6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。※特定商取引法 第70条
④両罰規定(法人にも罰則が科される)
違反を行ったのが法人の従業員や役員であったとして、その法人自体にも罰金刑が科されることがあります(両罰規定)。※特定商取引法 第73条
営業担当者が不実告知をした場合、本人だけでなく会社にも罰金が科される可能性あり
特商法に違反しないための対策
特商法に違反しないためには、対象となる取引類型や規制の内容を正しく理解し、社内での教育や研修を徹底することが重要です。
広告や勧誘の場面では、法令に基づいた正確な情報を提供し、クーリング・オフ制度など消費者の権利についても明確に伝える必要があります。
①社内研修による法令理解の徹底
まず重要なことは、従業員が特商法を正しく理解していることです。
訪問販売や電話勧誘販売を行う企業では、営業担当者が直接消費者と接するため、誤った説明や違法な勧誘が発生しやすい傾向にあります。
社内での定期的な法令研修やチェックリストの活用を通じて、ルールの周知と遵守を徹底しましょう。
②広告・表示内容の法令チェック体制の整備
広告や販促資料には、価格、支払条件、契約期間などの「重要事項」を正確に表示する必要があります。
とくに通信販売では、虚偽表示や誇大広告が問題となりやすいため、広告内容を事前に法務・コンプライアンス部門がチェックする体制を構築することが重要です。
「初回無料」「定期購入の縛りなし」など、誤解を招きやすい表現には十分な注意が必要です。
③クーリング・オフなど消費者の権利を正しく案内
特商法では、取引類型ごとにクーリング・オフ制度が設けられています。
事業者は契約時に、消費者に対してその制度の有無や手続き方法を、書面で正確に説明する義務があります。
説明不足や誤った案内は法令違反となり、後にトラブルへと発展することも。
クーリング・オフや契約解除に関する説明は、書面・口頭の両面で丁寧に行うようにしましょう。
特商法に基づく表記の例
以下では「特定商取引法ガイド」の内容をもとに、どのような点が不適切か、そしてどう改善すべきかをわかりやすく解説します。
①事業者の氏名等
特商法に基づく表記では、販売者の氏名または会社名を正確に記載する必要があります。
会社であれば商業登記簿上の正式な名称を、個人事業主であれば戸籍上の氏名を使用し、通称名や屋号、サイト名だけの表示は認められません。
株式会社〇〇〇〇
特商法に基づく表記は個人事業主にも適用される?
特商法に基づく表記は個人事業主にも適用されます。
特商法では、広告に事業者が実際に活動している住所と、確実に連絡が取れる電話番号を表示する必要があります。
これは、トラブル対応や消費者からの問い合わせに備えるためのものです。ただし、以下の条件をすべて満たす場合には住所や電話番号の表示を省略することも可能です。
- 広告上に「消費者から請求があった際に、書面や電子メールで「遅滞なく」情報を提供する」旨を明記している。
- 実際に消費者から請求があった際に「遅滞なく」迅速な対応ができる体制が整っている。
ここでいう「遅滞なく」とは、消費者が申込み前に十分な時間をもって情報を入手できることを意味します。
②事業者の住所、電話番号
住所は、実際に事業活動を行っている場所を正確に記載する必要があります。番地の省略や私書箱のみの記載は認められていません。
東京都中央区京橋(番地が省略されている)
電話番号は、消費者からの問い合わせに対応できる番号を記載します。24時間対応である必要はなく、受付時間を明記すれば問題ありません。また、連絡手段に優先順位がある場合は、その旨も記載しておくと親切です。
電話番号:03-1234-5678
受付時間:10:00〜18:00(土日祝を除く)
※受付時間外はメールでご連絡ください。
③商品の販売価格
販売価格は、税込の実際の価格を明確に表示する必要があります。商品点数が多い場合は「各商品ページをご参照ください」と記載しても問題ありません。
1,980円(税込)
また、送料や手数料など商品以外にかかる費用も、項目ごとに具体的な金額を記載する必要があります。「実費」「手数料がかかります」といったあいまいな表現はNGです。
- 配送料の例:宅急便〇〇円、メール便〇〇円
- 手数料の例:コンビニ決済〇〇円、代金引換〇〇円
- 送料無料の例:全国一律〇〇円(5,000円以上の購入で送料無料)
④支払い方法と支払いの時期
支払方法は、利用可能な決済手段をもれなくすべて記載する必要があります。記載漏れがないよう注意しましょう。
支払時期は、消費者がいつ代金を支払うのかを明確に伝えることが求められます。複数の支払方法がある場合は、それぞれのタイミングを個別に記載しましょう。
- コンビニ決済:ご注文後〇日以内にお支払いください。
- 代金引換:商品到着時に、配達員へ現金でお支払いください。
- クレジットカード決済:ご注文時に決済が完了します。
- コンビニ決済・代引きの場合は手数料が発生いたします。
※これは手数料の説明であり、支払時期が明記されていないため不十分です。
⑤商品の引き渡し時期
商品の発送時期は、具体的な日数で明記する必要があります。
「ご注文確認後に発送」などの曖昧な表現では、発送までの期間が不明確で、法令上不適切な表記とし、消費者に誤解を与える可能性があります。
- ご注文日から〇営業日以内に発送いたします。
- ご注文確認後、速やかに発送いたします。(通常、発送までに3営業日ほどかかります。天候や配送業者の都合により遅れる場合は、事前にご連絡いたします)
⑥返品や交換について
返品や交換の可否、条件、送料の負担については明確に記載する必要があります。あいまいな表現はトラブルの原因になるため避けましょう。
- 商品到着後〇〇日以内であれば返品・交換が可能です。送料は、商品に欠陥がある場合は当社負担、それ以外の場合はお客様のご負担となります。
- お客様都合による返品・交換はお受けしておりません。商品に不備があった場合は、到着後〇〇日以内にご連絡いただければ、当社負担で対応いたします。
「商品に欠陥がない場合の返品については、その都度ご相談に応じます」
→ 条件や期限、送料負担が不明で不適切。
その他
販売者の情報を正しく記載していても、消費者がその情報を見つけられなければ意味がありません。そのため、表記は消費者が見つけやすい場所に掲載することが重要です。
たとえば、販売ページ内にアコーディオン(折りたたみ)形式で記載する方法でも問題ありません。ただし、その内容を購入前に消費者が確認できるようにすることが重要です。
「すべての内容を表示・確認し、チェックを入れないと購入画面に進めない」といった仕組みを設けておけば、法令上も適切とされます。
消費者が購入前にきちんと確認できるように記載をすることがポイントです。
まとめ
特定商取引法に基づく表記を正しく行うことは、消費者との信頼関係を築くための第一歩です。わかりやすく整理された販売者情報は「このお店なら安心できる」という信頼感を消費者に与えます。
小さな見落としがトラブルやリスクに繋がることもあるので、意識していきましょう。
この記事から学んでおきたい関連知識


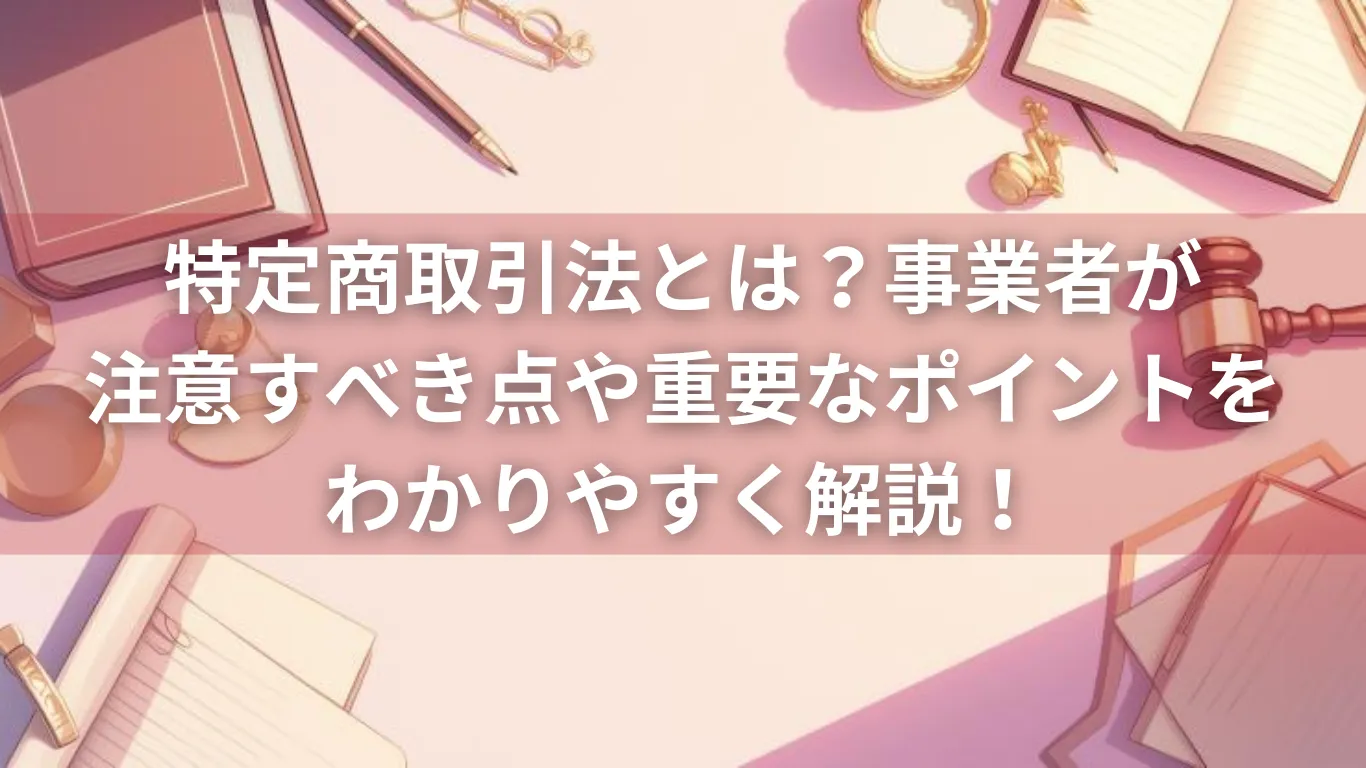
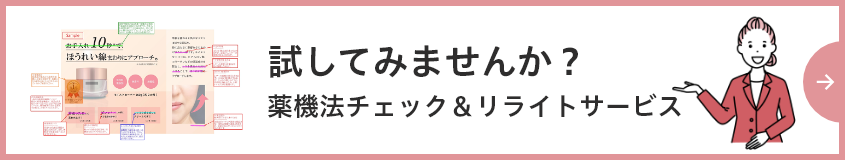


ECサイトやサービスを提供する事業者にとって「特定商取引法」は避けて通れない重要な法律です。
この法律は、事業者に適正な取引ルールを守らせるとともに、消費者がトラブルから身を守る仕組みも定めています。
違反をした場合には、行政処分や罰則の対象となる可能性もあります。
本記事では、特定商取引法の基本的な内容から、事業者が特に注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >