Contents
薬機法とは
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
薬機法は、化粧品や医薬部外品、医薬品等や医療機器等の取扱いについて定めた法律であり、厚生労働省がとりまとめているものです。以前は「薬事法」という名称でした。
規制対象には、医薬品だけでなく化粧品や医薬部外品も含まれています。製品の容器や包装に表示しなければならない内容や、広告表現の細部に至るまで、化粧品や医薬部外品などの製造・販売に関わるルールは主に薬機法に定められています。
薬機法の目的
薬機法の目的は、主に2つあります。
ひとつは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保や、これらの使用による保健衛生上の危害の発生と拡大を防止するために必要な規制を行うことです。
医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器等は、私たちの生活に欠かせないものと言えます。薬機法は、それらの安全性を確保し、使用により健康を害することの防止を目的の一つとしています。
もうひとつは、指定薬物の規制に関する措置を講じ、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること、となっています。
薬機法規制の対象となるもの
それでは、どのようなものが薬機法規制の対象となっているのでしょうか。
主に、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品が規制対象となっています。中でもこれらの広告表現については、「医薬品等適正広告基準」に非常に詳細に規制内容が示されています。
また、上記の医薬品等や医療機器・再生医療等製品以外に、雑貨や健康食品、機能性表示食品の標ぼうについても、薬機法にて規制されています。
雑貨や食品は、医療機器や化粧品、医薬部外品、医薬品などには該当しません。
しかしながら、雑貨や食品であるにもかかわらず、
「骨盤の歪みが治った!」
「頑固な便秘が治った!」
など、医療機器や医薬品であるかのような効能効果を標ぼうしている広告を皆さまも一度はご覧になったことがあるかと思います。
このように、医療機器や医薬品のフリをした雑貨や食品は、医療機器や医薬品としての承認や許可を得ていない、無承認無許可の医薬品・医療機器とみなされ、薬機法の規制対象となります。
また、薬機法においては、第六十六条、第六十八条の「何人(なんぴと)も~してはならない」という文言が示す通り、事業者だけでなく、全ての人が規制対象となります。
つまり、広告主である事業者以外にも、アフィリエイターやインフルエンサーによる医薬品等の広告表示の内容も薬機法の規制対象となっているということです。
ヘアカラーリング製品は薬機法の広告規制の対象となる
ここまで、薬機法の目的や規制対象について解説しました。それでは、冒頭で触れた「ヘアカラーリング製品」は薬機法の広告規制対象に含まれるのでしょうか?
答えは「YES」です。
ヘアカラーリング製品は薬機法の広告規制対象に該当します。ここから、ヘアカラーリング製品が薬機法上どのように分類され、どのようなルールが適用されるのかについて、簡潔に説明します。
化粧品か医薬部外品に該当する
ヘアカラーリング製品は一般的に「医薬部外品」および「化粧品」に分類されます。薬機法第2条第3項では、化粧品について次のように定義されています。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
引用元:e-eov 法令検索
簡単に言えば、「化粧品とは、美容や清潔、健康を目的に人の体に直接塗ったり付けたりするもので、医薬品ほどの強い作用はないもの」と定義できます。この定義に基づくヘアカラーリング製品は化粧品に分類されます。
一方、医薬部外品のヘアカラーリング製品もあります。薬機法第2条第2項では医薬部外品について次のように定義されています。
「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止、あせも・ただれの防止、脱毛防止・育毛・除毛等の目的で使用される物
二 保健衛生の目的で特定の生物を防除する物
三 厚生労働大臣が指定する物引用元:e-eov 法令検索
まとめると、「医薬品ほど明確な作用はないが、一定の薬効が認められた厚生労働省承認のもので、機械器具ではないもの」が医薬部外品に該当します。医薬部外品として販売されているヘアカラーリング製品も多く、化粧品と医薬部外品の両方が薬機法の対象となります。
化粧品における薬機法のルール
ヘアカラーリング製品が薬機法上、化粧品または医薬部外品に該当することを踏まえ、これらに適用される具体的なルールについて説明します。
まず、化粧品および医薬部外品には容器やパッケージに表示すべき事項が定められています。商品の名称や成分などの情報を明記することが求められ、これらがパッケージで隠れる場合には外側にも表示が必要です。また、保健衛生の観点から法定表示も含まれます。
さらに、広告表示に関するルールとしては、以下の点が挙げられます。
- 誇大広告の禁止
医薬品等の名称、製造方法、効能・効果について虚偽や誇大な内容を明示・暗示する広告は禁じられています。 - 医薬品等適正広告基準
厚生労働省が定めたこの基準は、化粧品や医薬部外品を含む医薬品等の広告表現に関する詳細なルールを示しています。
また、日本化粧品工業連合会が策定した「化粧品等の適正広告ガイドライン」も重要です。このガイドラインは業界の自主基準ですが、具体例を交えて広告表現の適切さを判断する際の指針となります。
医薬品等適正広告基準を補足する内容が網羅されているため、ヘアカラーリング製品含む化粧品広告に携わる方には必読の資料です。
医薬部外品における薬機法のルール
医薬部外品は、医薬品ほど強い効果は持たないものの、化粧品よりも高い効果を発揮する中間的な製品です。厚生労働省が認めた有効成分を含み、予防や衛生を目的として使用されます。
この特性により、医薬部外品は特定の効能や効果を標ぼうすることが可能ですが、その範囲は限定されています。具体的には、次の特徴が挙げられます。
- 身体への作用が緩和であること
医薬部外品は、身体への効果が穏やかで、副作用のリスクが低いことが特徴です。そのため、安全性を重視した製品として幅広く使用されています。
- 特定の目的に応じて使用する
医薬部外品は、以下の目的に合わせて使用される製品が含まれます。
- 吐き気や不快感、口臭・体臭の防止
例として、口臭を抑えるマウスウォッシュや、体臭対策のデオドラント製品が該当します。 - あせもやただれの予防
あせも予防用のパウダーやクリームなどがこれに含まれます。 - 脱毛防止や育毛、除毛
育毛トニックや除毛クリームといった製品も医薬部外品として扱われます。 - 特定の生物の防除
人や動物の健康を守るため、蚊やハエ、ネズミといった害虫の駆除を目的とした製品も対象となります。例として虫よけスプレーやネズミ駆除薬が挙げられます。 - 厚生労働大臣が指定したもの
さらに、厚生労働大臣が特定の用途のために認可した製品も医薬部外品に含まれます。これにより、製品が一定の効果と安全性を有することが保証されています。
ヘアカラーも含む医薬部外品は、化粧品以上の効能を求める消費者のニーズを満たす一方で、安全性の確保や適切な使用目的の明示が求められる製品です。
【そのまま使用OK!】ヘアカラーリング製品の広告に使える表現一覧
ここからは、ヘアカラーリング製品の広告において、実際にどのような表現が可能なのかを、化粧品の場合・医薬部外品の場合に分けてご紹介します。
化粧品と医薬部外品では言える範囲がかなり変わってきますので、広告を作成する際には、扱う商品がどちらに分類されるのかを事前に製造販売元にご確認いただくことをおすすめいたします。
染毛料(化粧品)で使用可能な表現
化粧品のヘアカラーリング製品は「染毛料」と呼ばれ、ヘアマニキュアやカラートリートメント、ヘアカラースプレーなどが含まれています。
化粧品のヘアカラーリング製品で使用可能な表現は、化粧品の56の効能効果の範囲内および物理的な着色によるもののみで、脱色や薬理的作用による染色は謳えませんので注意が必要です。
| No | 広告表現 | 訴求したい効果 |
|---|---|---|
| 1 | 毎日できるカラーケア | カラーシャンプーやカラートリートメントなどを毎日使用することで着色される |
| 2 | 傷んだ髪をケアしながら染める | 着色と同時に傷んだ髪のケアもできる(化粧品なので髪の補修の標ぼうも○) |
| 3 | ヘアカラー後の色落ち対策に | 美容室などでのヘアカラー後に褪色していく髪に、カラーシャンプーなどで着色して色持ちしているように見せる |
| 4 | パープルで黄ばみを抑える | 染毛料の物理的な着色により髪の黄ばみを抑える |
| 5 | オイル配合で乾燥やパサつきを抑える | うるおいを与えることで髪の乾燥を抑える(化粧品なので髪の保湿の標ぼうも○) |
染毛剤(医薬部外品)で使用可能な表現
医薬部外品のヘアカラーリング製品は「染毛剤」と呼ばれ、ヘアカラー、おしゃれ染め、白髪染め、ヘアブリーチなどが含まれています。
医薬部外品で使用可能な表現は、承認された薬効の範囲内までとされています。
ちなみに染毛剤は医薬部外品であり、薬用化粧水や薬用美容液、薬用歯磨きなどのように化粧品効能を標ぼうすることは認められていませんので、注意が必要です。
| No | 広告表現 | 訴求したい効果 |
|---|---|---|
| 1 | 5分でしっかり白髪染め | 白髪染めの手軽さ |
| 2 | リタッチだけならこれでOK | おしゃれ染め、白髪染めの製品での部分染めの手軽さ |
| 3 | おうちでサロン級ヘアカラー | 仕上がりの良さ(「美容室」と書くと医薬関係者等の推薦表現にあたるため×) |
| 4 | 透明感カラーに染める | 色の良さ(「透明感」はスキンケアでは不可となる場合もありますが、染毛剤は色の透明感として標ぼうも差し支えありません) |
| 5 | ふんわり泡でセルフブリーチ | 泡の使用感の良さ |

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのヘアカラーリング製品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。
弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。
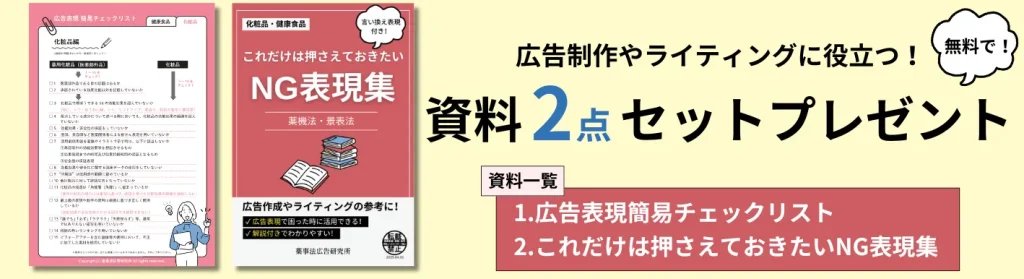
よくあるNG表現
次に、ヘアカラーリング製品の広告でよくあるNG表現をご紹介します。
薬機法のルール上言えない、効果の保証、安全性の保証、医薬関係者等の推薦といった表現だけでなく、化粧品のカラートリートメントで医薬部外品のような効果を述べたり、医薬部外品のヘアカラーで化粧品の効果を述べたりと、それぞれの商品で言えない効果を使用してしまうといったケースもよくある印象です。
NG表現①「美容師もおすすめ!」
「美容師もおすすめ!」は、化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。
ヘアカラーリング製品について、美容師さんが「おすすめです」と言っていたら、品質がよさそう、プロの現場でも使えるぐらい性能が良さそう、と思ってしまうものです。でも実際の内容はほかの商品とさほど変わらないということも往々にしてあります。
そのような誤認をできるだけ抑えるため、医薬品等適正広告基準において、理容師、美容師などによる化粧品・医薬部外品などの推薦は、医薬品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与えるとして禁止されています。
言い換え案:美容業界も注目!
NG表現②「初めてでも安心して使えます」
「初めてでも安心して使えます」は、化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。「安心」とすることで安全性を保証する表現となり、薬機法上不可となります。
また、日本ヘアカラー工業会の『染毛剤の表示・広告に関する自主基準』では、医薬部外品の染毛剤の商品において「初めての方でも安心して使用できます」といった表現は不適当としています。
医薬部外品の染毛剤は使用法を誤れば毛髪等の損傷を招くおそれがありますし、事前にパッチテストが必要となるものもあり、安易に「手軽」「安心」といった表現をするべきでないとしています。
言い換え案:使いやすい容器で便利
NG表現③「どんな髪でも染まる」
「どんな髪でも染まる」は、化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。あらゆる髪の毛に効果があるかのような効果を保証する表現となり、薬機法上不可となります。
また、化粧品の染毛料においては、「染まる」という表現を使用する際、医薬部外品との誤解を与えないよう、「※物理的着色による」など化粧品効能を逸脱しない物理的効果であることが明確に伝わるような記載が必要です。
言い換え案:しっかり染まる (化粧品の場合は「※物理的着色による」と注釈を付記)
NG表現④「髪から若返る!」
「髪から若返る!」は、化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。化粧品や医薬部外品においては、老化防止や若返りと言ったアンチエイジング的な効果の標ぼうは認められていません。
比喩だとしても、若返るかのように読めてしまえばNGとなりますので、極力誤解を招かないような言葉選びが必要です。
白髪を染めることで印象が若々しく変わることについて述べるのであれば、あくまで「髪を染めたことにより若く見える」の範疇に留めましょう。
言い換え案:髪から若見え!
NG表現⑤「カラーしながら髪質改善」
「カラーしながら髪質改善」は化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。
化粧品の場合、「髪質改善」は化粧品効能の中にない効果の表現であり、効果の逸脱となります。医薬部外品の染毛剤の場合、「髪質改善」の薬効を持っていない限りは、承認されていない効能効果として不可となります。
なお、医薬部外品では承認された薬効以外のことを述べられませんが、化粧品のカラートリートメントなど毛髪の補修の効果が謳えるものについては、髪質改善ではなく毛髪ダメージの補修を訴求できます。
言い換え案:カラーしながら髪のダメージも補修(化粧品のみ可な表現)
薬機法に違反してしまった場合の罰則
ここまでの内容では、化粧品や薬用化粧品の美容液に関する広告表示について、薬機法のルールを解説してきました。では、万が一これらのルールを逸脱し、薬機法に違反した場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。
薬機法における主な罰則には、「刑事罰」「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」があります。ここでは、その中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」について簡単に解説します。
行政指導
「行政指導」とは、行政機関が違法状態の是正を命じる是正措置のことです。
その中でも代表的なのが、違反となる広告表現を修正するよう指示する「是正命令」です。また、違反内容や是正措置に関する報告書の提出を求められる場合もあります。
行政指導が行われるきっかけとしては、行政機関が行う監視活動で違反が発覚する場合や、消費者からの苦情が寄せられ調査が開始される場合が挙げられます。また、同業者による違反の情報提供によって違反が発覚し、指導が入るケースもあるようです。
措置命令
「措置命令」とは、厚生労働大臣や都道府県知事が違反者に対して発動する命令です。
この命令は、薬機法第66条第1項で定められた誇大広告の禁止や、第68条で定められた未承認医薬品等の広告禁止に違反した場合に下されます。
措置命令の内容としては、違反行為を即時中止する「行為の中止命令」、再発防止策を求める「再発防止措置」、公衆衛生上の危険を防止するための「公示命令」があります。こちらは違反したことを公に周知しなければならないため、顧客からの信頼を失うリスクもあります。
課徴金納付命令
「課徴金納付命令」は、薬機法第66条第1項に定められた誇大広告禁止に違反した場合に科されるものです。課徴金額は、課徴金対象期間における医薬品等の取引対価総額の4.5%とされます。ただし、課徴金額が225万円未満の場合は納付命令は出されません。
課徴金対象期間は、原則として虚偽・誇大広告等を行った期間が該当します。また、虚偽・誇大広告等を中止してから6ヶ月以内に、名称や効能などで誤解を生じさせないための措置を講じない場合や、取引が継続している場合には、最長3年間が対象期間に含まれることになります。
薬機法に違反しないための対策
美容液の広告表現において薬機法違反を防ぐには、どのような対策が必要でしょうか。
「化粧品の広告を作りたいけど、薬機法が複雑で不安…」
「自社の広告が薬機法に違反していないか自信が持てない…」
こうした悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。ここでは、薬機法違反を防ぐために今すぐ実践できる3つの対策をご紹介します。
①薬機法に関する社内研修を実施する
対策の一つ目は、「薬機法に関する社内研修を実施すること」です。特に化粧品広告を扱う企業では、社員に対するコンプライアンス教育の一環として研修を行うことが重要です。
東京都が開催する「事業者向けコンプライアンス講習会」「医薬品等広告講習会」や、各業界団体が主催する化粧品関連セミナーへの参加もおすすめです。また、民間企業が提供している薬機法や化粧品広告表現に特化したセミナーを活用する方法もあります。
これにより、社員が薬機法の基本的なルールを理解し、広告制作時にルールを守る意識を高めることができます。
②広告作成は2人体制で行う
対策の二つ目は、「広告作成を二人体制で行うこと」です。
一人で作業を進めると、見落としや誤りが発生しやすくなります。そのため、二人体制でダブルチェックを行うことが効果的です。特に、薬機法の知識を持つ者同士がチェックを行うことで、広告表現の精度を高めることができます。
このようなダブルチェックの仕組みは、他の業務においてもヒューマンエラーの防止に効果があると広く認識されており、比較的ポピュラーな方法です。
③広告チェックサービスを活用する
三つ目の対策は、「広告チェックサービスを活用すること」です。
薬機法を遵守した広告を作成したいものの、扱う商品数や出稿量が多い場合、社内のチェック体制だけでは限界があることもあります。こうした場合には、外部の広告チェックサービスを利用するのも有効な手段です。
これらのサービスでは、広告表現のチェックだけでなく、リライトを行うサービスや、薬機法や景品表示法を踏まえたセミナーや研修も提供しています。自社のニーズに合ったサービスを選び、効率的に広告の品質を向上させましょう。
④過去の違反事例を知る
四つ目の対策は、「過去の違反事例を知る」ことです。
過去に薬機法違反で処分された事例を確認し、どのような点が問題となったのかを学ぶことで、NGとなる広告表現は何かが見えてきます。
薬機法だけでなく、景品表示法に基づき措置命令が下された事例も参考になります。例えば、化粧品や医薬部外品が優良誤認(不実証広告)の指摘を受け、問題視された事例などを消費者庁のホームページなどを中心に詳しく調べることで、問題となる表現がどのようなものか具体的に理解する手助けになるでしょう。
まとめ
ヘアカラーリング製品の広告は、特に人を惹きつけるような言葉で魅力的に見せたいもの。
しかしながら、薬機法や景品表示法など、法律を無視して広告を作成してしまうと、措置命令を受けたり、課徴金を支払ったり、社会や顧客からの信頼を失ったりと、自分の首を絞める結果につながってしまいます。
だからこそ、今回の記事で紹介した、下記のポイントは是非押さえていただけたらと思います。
- 薬機法の基本ルールを理解する
- 化粧品と医薬部外品の違いを理解する
- 過去の違反事例をリサーチして、NGとなる表現を学ぶ
- 社内でダブルチェック体制を作る
- 困ったらプロの広告チェックサービスに頼ることも検討
広告で消費者を引きつけるのは大切なことです。しかし、「安全で正しい広告を作る」ことが結果的に信頼につながり、商品や企業が長く愛されることに繋がっていきます。
ルールを守って、ヘアカラーリング製品の魅力をしっかりとアピールしていきましょう。
この記事から学んでおきたい関連知識



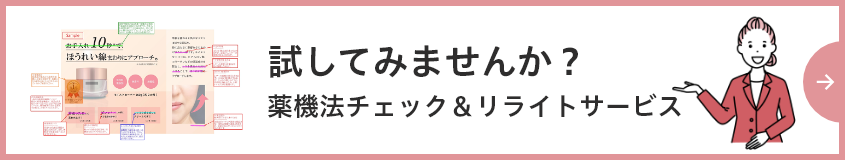


ヘアカラーリング製品の広告を展開する際には、魅力的な表現を使いながらも、薬機法をはじめとする法律を遵守することが求められます。
しかし、「どこまで言っていいのか」「何が違反になるのか」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
たとえばヘアカラーは医薬部外品に分類されており、広告においても効果や効能をアピールできる範囲が明確に定められています。一方で、カラートリートメントなど、化粧品で販売されているヘアカラーリング製品もあります。
今回の記事では、薬機法の基本ルールをわかりやすく解説し、実際の広告作成で注意すべきポイントをお伝えします。正しい知識を持ち、安全かつ魅力的な広告を打ち出すためのヒントをぜひ参考にしてください。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >