Contents
薬機法とは
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、医薬品等の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、流通、販売、広告などに関するルールを定めた法律です。
薬機法の規制対象となる商品の製造・販売に関わる事業者は、その内容を十分理解し、定められたルールを遵守する必要があります。
薬機法の目的
薬機法は、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保するための規制を設けることで、国民の健康を守り、保健衛生上のリスクを未然に防ぐことを目的としています。
薬機法の規制対象となる製品は人の身体に直接作用するため、その品質や安全性が確保されていなければ重大な健康被害を引き起こす可能性があります。薬機法では、こうしたリスクを抑えるために製造・販売に関する厳格な基準が定められています。
さらに、消費者を誤解させる広告表現を防ぐことも重要な役割の一つです。これにより、消費者が安全かつ信頼できる製品を選べるようにし、健全な市場環境を維持することにも寄与しています。
薬機法規制の対象となるもの
薬機法の規制対象は、医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品の5つに分類されます。
- 医薬品
病気の予防や治療、診断を目的とし、その成分が人体に直接作用するもの - 医療機器
診断や治療、予防に使用される装置や器具、検査機器など - 再生医療統制品
細胞や組織を利用し、人体の機能や構造を回復または再生させることを目的としたもの - 医薬部外品
医薬品ほどの強い作用は持たないものの、健康維持や美容効果が期待できる製品で、効能や成分が限定されている - 化粧品
美化や清潔の保持を目的とし、人体に及ぼす作用が穏やかな製品
いわゆる健康食品や雑貨は薬機法の規制対象ではありませんが、医薬品や医療機器と誤認される広告表示をした場合は規制されます。
トリートメントは薬機法の広告規制の対象となるか
では、トリートメントは薬機法の広告規制の対象になるのでしょうか。
トリートメントが属する商品カテゴリから考えてみましょう。
化粧品か医薬部外品に該当する
トリートメントは、化粧品に分類されるものと医薬部外品(薬用化粧品)に分類されるものがあります。
化粧品の場合、頭皮、毛髪を保湿したり毛髪にツヤを与えたりする目的で使用されます。医薬部外品の場合は頭皮、毛髪の保湿等に加えてふけ・かゆみの予防などの効果を持つものもあります。
化粧品と医薬部外品はいずれも薬機法の規制対象であり、製造・販売・広告を行う際には、薬機法に基づいた適切な対応が求められます。
化粧品・薬用化粧品における薬機法のルール
ここでは、化粧品と薬用化粧品の広告表現に関するルールをご紹介します。
基本的なルールは「医薬品等適正広告基準」にまとめられていますので、化粧品・薬用化粧品の広告に携わる方は是非確認してみてください。
この中で、広告表現を行う際に特に注意したいのは下記の内容です。
- 製造方法について、事実と異なる表現や誇大な表現をしてはならない。
- 承認を受けた効果の範囲もしくは医学、薬学上認められている効果の範囲を超えた表現をしてはならない。
- 効能効果・安全性を保証するような表現をしてはならない。
- 効能効果・安全性についての最大級の表現またはこれに類する表現をしてはならない。
- 品質・効能効果・安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。
- 医薬関係者が推薦しているような表現をしてはならない。
②の効果の範囲について、化粧品の場合は56項目の効果の範囲が定められています。そのうち、ヘアケア製品に関係するものは次の16項目です。
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
薬用化粧品の「リンス」の効能効果は
・ふけ、かゆみを防ぐ。
・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
・毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
・裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
・毛髪・頭皮をすこやかに保つ or 毛髪をしなやかにする。
となりますが、薬用化粧品の場合、上記の内容に加えて化粧品の効果も表現できます。
【そのまま使用OK!】トリートメントの広告に使える表現一覧
トリートメントの広告で使える具体的な表現例をご紹介いたします。
普段、顔に塗るスキンケア商品等の広告表現を行っている方は、「補修」や「内部」という表現が気になってしまうかもしれませんが、毛髪に対する効果としては表現可能な範囲となります。
毛髪への浸透表現については、化粧品等の適正広告ガイドラインでも以下のような説明がされていますので参考にしてください。
「毛髪への浸透」等の表現
「毛髪への浸透」表現は、角化した毛髪部分の範囲内で行うこと。
[表現できる例]
髪の内部へ浸透、髪の芯まで浸透
[表現できない例]
傷んだ髪へ浸透して健康な髪へ甦ります(回復的)
以下の例は、化粧品・薬用化粧品のどちらでも使用することができます。
| No | 広告表現 | 訴求したい効果 |
|---|---|---|
| 1 | ダメージヘアを補修する | 傷んだ髪のケア |
| 2 | 枝毛・切れ毛が気になる方に | 傷んだ髪のケア |
| 3 | ●●(成分)がキューティクルを健やかに | 傷んだ髪のケア・浸透 |
| 4 | 髪の内部まで浸透する | 浸透 |
| 5 | 傷んだ髪の芯までケア | 浸透 |
| 6 | (悩み表現)乾燥で地肌が硬い | 頭皮の保湿 |
| 7 | 髪の静電気対策 | 帯電の防止 |
| 8 | 広がりを抑えてまとまる髪に | 美髪 |
| 9 | 毎日サロン帰りのようなツヤ髪 | 美髪 |
| 10 | ●●の香りでヘアケアがリラックスタイムに | 癒し |

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのトリートメントならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。
弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。
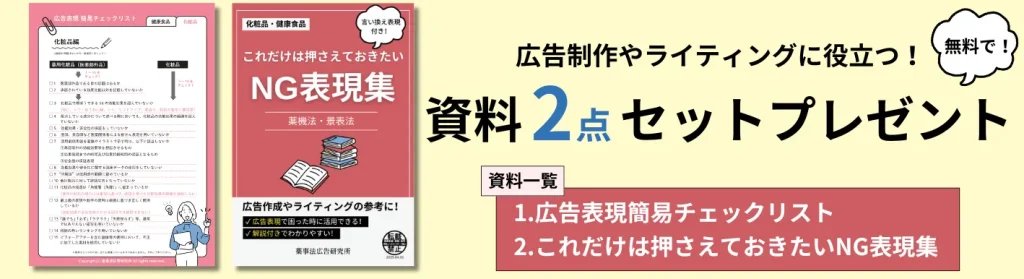
よくあるNG表現
次に、よくあるNG表現をご紹介します。
化粧品・薬用化粧品のトリートメントは、物理的な補修効果であれば表現できますが、治療のような表現はできないため注意が必要です。
NG表現①「髪を修復する」
「補修」と混同してうっかり使用しないように気を付けたいのが「修復」という言葉です。「修復」の場合、毛髪の損傷部分が治療的に回復するような表現と捉えられるためNGとなります。
化粧品等の適正広告ガイドラインにも「認められない表現の具体例」として掲載されている代表的な表現なので、しっかり認識しておきましょう。
NG表現②「髪を蘇らせる/再生する」
先ほども触れた毛髪の「補修」の程度に関して、化粧品等の適正広告ガイドラインで次のように定義されています。
- 毛髪の損傷等とは、物理的刺激あるいは化学的処理により毛髪からその構成成分が損失し、毛髪表面や内部組織の物性変化や剥離、空隙等が発生して傷んだ状態のことである。
- 毛髪の補修とは、損傷毛髪に対して、化学反応や薬理作用を伴わない補修成分を、表面に被覆あるいは内部浸透させて、表面や内部の損傷部位の空隙の密着等により、物理的に損傷を補い繕うことであり、治療的な回復のことではない。
この内容を踏まえると、「髪が蘇る」「髪の再生を助ける」のような表現は、「補修」を超えた治癒的な回復と捉えられることになります。
「頭皮にうるおいを与え、健やかな髪の土台を整える」など、健康な髪をイメージさせるような表現を使用しましょう。
NG表現③「うねりを改善(髪質改善)」
髪のうねりを根本から改善、つまり髪質が改善するような表現は不可となります。
髪質そのものではなく、保湿やコーティングにより状態を変化させる表現であれば可能となりますので「うねりを抑える」「うねりをケアする」程度の表現を使用しましょう。
NG表現④「地肌(頭皮)の血行促進」
頭皮をすこやかに保つという効果に関連して血行促進を標ぼうしようとする広告がみられますが、商品や成分の効果と説明してしまうと化粧品効能の範囲の逸脱となります。
血行促進については、商品を使用して行うマッサージによる効果であることを明確にすれば使用可能です。
NG表現⑤「育毛効果がある」
髪や地肌を健やかにするという効果の延長で、育毛にも効果があるような標ぼうをしないよう注意が必要です。
例えば、悩みの例として「切れ毛・枝毛・抜け毛にお悩みの方」のような表現をすることはできません。「切れ毛・枝毛・髪のパサつきにお悩みの方」など、化粧品効能の範囲内の表現にとどめてください。
NG表現⑥「かゆみの鎮静」
化粧品では「フケ、カユミがとれる。」「フケ、カユミを抑える。」、薬用化粧品では「ふけ、かゆみを防ぐ。」という効果を標ぼうすることができますが、「かゆみを鎮める」というような表現はできません。(治癒的な表現のため。)
また、「かゆみから解放された」等の表現については効果の保証となるため「かゆみが気にならなくなってきた」程度の表現にとどめましょう。
薬機法に違反してしまった場合の罰則
ここまで、トリートメントの広告と薬機法がどう関わってくるか解説いたしましたが、もし薬機法に違反した場合にどのような罰則があるのでしょうか。
薬機法は、医薬品等の安全性を確保する上で重要な法律であるため、違反した場合には厳しい罰則が科せられます。罰則の内容を把握し、ルールを遵守する重要性を再認識しましょう。
ここでは、薬機法違反に対する罰則のうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明いたします。
行政指導
薬機法違反が認められた場合、まず行政指導が行われることがあります。
行政指導は、違反内容を指摘し、改善を求める非強制的な措置です。一般的に、違反の程度が軽微で、企業が速やかに対応可能な場合に適用されます。
具体的には、問題の広告の修正や取り下げ、今後の再発防止策の提出が求められます。
この段階では命令や罰則は伴いませんので、指導を受けた際には迅速かつ適切な対応が重要です。
措置命令
措置命令は、薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)および第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の違反に対して科されるものです。
違反の程度が重大で、消費者に誤解を与える恐れが高い場合に発令されます。
措置命令は強制力を伴い、違反広告の取り下げや是正措置の対応が求められます。また、消費者保護の観点から、適正な情報提供を行うことも命じられる場合があります。措置命令が下されると公表されるため、企業の信用に大きな影響を及ぼします。
課徴金納付命令
課徴金納付命令は第66条第1項(誇大広告等の禁止)に違反する行為に科されるものです。
対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4.5%を納付することが求められます(最低額は225万円)。
この命令は、消費者被害の救済や再発防止を目的としています。違反企業にとっては財務的負担が大きく、信用失墜のリスクも高まるため、違反を未然に防ぐための適切な広告管理体制が求められます。
薬機法に違反しないための対策
薬機法に違反した場合に、企業は多大なダメージを受けるということが十分にご理解いただけたのではないでしょうか。
ここからは、薬機法に違反しないための具体的な対策をいくつかご紹介いたします。
①薬機法に関する社内研修を実施する
薬機法違反を防ぐためには、社内研修を通じた社員教育が重要です。担当業務や知識レベルに応じた研修を行うのが効果的です。
例えば、新人に対しては薬機法の基本概念やポイントを端的に説明し、法令順守の重要性を浸透させる研修を行い、商品開発や広告を担当する専門部門へは、業務内容に即した表現方法や代替案を提示したり、過去の違反事例を共有し、業務に活かせる深い知識を提供するような研修を行うと良いでしょう。
また、定期的に研修を計画し、法律が改正された場合などに最新の情報を社内に共有できる体制を構築しておくことが重要です。
②広告作成は2人体制で行う
一人で作業を進めた場合、どうしても想定外のミスが起きてしまうものです。また、その場合にリカバリすることが難しくなります。
こうしたリスクを低減するため、ダブルチェックや複数部署による確認体制を取ることが求められます。複数名でのチェックは、ヒューマンエラーや軽微な見落としを減らすだけでなく、制作物の完成度を向上させることも期待できます。
同じ部署内で複数人のチェックをするよりは、複数部署で、それぞれが注視する範囲を決めて実施するのが良いでしょう。
③広告チェックサービスを活用する
広告には、今回ご紹介した薬機法だけでなく、景品表示法、健康増進法、特定商取引法など、様々な法律が関係してきます。これらの法律を、広告担当者が全て理解した上で適切な広告を制作するというのは現実的には難しいと思われます。
複数人でチェックを行う体制ができていたとしても、広告の出稿数が増加した場合、社内だけではチェックの人工を確保することが難しくなるかもしれません。
そんな時は、専門サービスにチェック業務を外注することが有効です。現在は、広告のチェック、リライト案の提案、セミナー、AIツールの提供など、さまざまなサービスが存在しますので、自社の不足分を埋められるものを見つけて活用してください。
まとめ
今回は、薬機法の基礎知識と、トリートメントの具体的な広告表現をご紹介しました。
薬機法の概要を理解していても、実際の広告表現を作成する際には適切な表現に迷うことも多いと思われますので、本解説が広告制作の参考となれば幸いです。
この記事から学んでおきたい関連知識



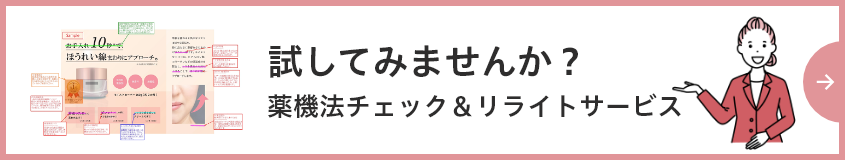


トリートメントは、髪に潤いとツヤを与え、傷んだ髪を補修することで美しい印象を作り出してくれるケアアイテムです。では、ヘアトリートメントを広告で紹介する際、どのような点に注意が必要でしょうか。
ヘアケア製品の製造販売や広告を行う際には、さまざまな法令が関わりますが、今回はその中でも薬機法との関わりに焦点を当てて解説します。また、そのまま使用できる表現事例もあわせてご紹介いたします。
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >