Contents
薬機法とは
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品が本法律の対象となります。対象商品の製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かいルールが定められており、対象商品を扱う事業者は、この法律を遵守する必要があります。
薬機法の目的
薬機法の目的は、第一条で下記の通り定められています。
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする
引用元:e-GOV法令検索
内容をまとめると、薬機法の目的は医薬品等の品質・有効性・安全性を確保することにあると言えます。
また、医薬品等を使用したことによる保健衛生上の危害の発生を防止するという目的もあります。そして、危害が発生した場合にはその拡大を防止するために必要な規制も行います。
薬機法規制の対象となるもの
薬機法が規制する「医薬品等」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品を指します。間接的ではありますが、健康食品もその対象になります。
具体的には、それぞれ下記のような製品が規制対象となります。
- 医薬品
病気の診断、治療、予防を目的に使用され、体の機能や構造に作用する成分を含む製品。
例:処方薬、一般用医薬品 - 医薬部外品
軽い作用で体の不快感を和らげたり、虫よけなどの効能を持つ製品。厚生労働省の承認を受け、特定の効能表示が可能です。
例:育毛剤、入浴剤 - 化粧品
体を美しく見せたり、肌や髪を健やかに保つ目的で使用される製品で、体への作用は穏やかです。
例:美容液、クレンジング、リップ - 医療機器
病気の診断、治療、予防や体の機能を補助する器具や機械。具体的な対象範囲は政令で定められています。
例:血圧計、マッサージ器具 - 健康食品
健康維持や増進を目的に摂取される食品の総称です。直接的な規制対象にはなりませんが、医薬品的な効能などをうたった場合に規制対象となります。
例:サプリメント、プロテイン
プロテインは薬機法の広告規制の対象となることもある
ここでは、薬機法におけるプロテインの扱いや広告のルールについて説明します。
プロテインは健康食品に該当する
プロテインは「食品」にあたります。また、食品の中でも、いわゆる健康食品に分類されます。
いわゆる健康食品とは、健康の維持や増進を目的として摂取される食品を指します。一般的には栄養補給や生活習慣病の予防を目的とした食品が健康食品にあたります。
さて、プロテインは「食品」に該当するため、原則として薬機法の規制対象ではありません。しかし、既にお伝えしている通り、薬機法が完全に無関係というわけではありません。
薬機法は、対象となる商品だけでなく、対象外の商品が規制範囲に該当する行為をすることも禁止しています。たとえば、単なる食品である健康食品でありながら、医薬品であるかのように誤解を与える表現は規制の対象となります。
事業者は通常、自社商品の区分を理解しているため、意図的に医薬品と偽ることはないはずです。しかし、広告表現が行き過ぎて消費者が医薬品と誤認する状況になれば、その商品は無許可で販売された医薬品と見なされ、薬機法違反に問われる可能性があります。
健康食品における薬機法のルール
食品(健康食品)は薬機法上、医薬品や医薬部外品には該当しませんが、表示内容が薬機法の規制対象となる場合があります。
特に、「医薬品的な効果効能を標榜する表現」は厳しく制限されています。たとえば、「血圧を下げる」や「関節の痛みを和らげる」といった表現は、医薬品以外では使用が許されません。
また、薬機法では「未承認医薬品の広告禁止」や「誇大広告の禁止」も規定されています。科学的根拠のない効果を謳ったり、医薬品であるかのような印象を与える表現は違法となる可能性があります。
これを防ぐためには、商品特性や成分を正確に理解し、法規制の範囲内で適切な表現を行うことが重要です。
参考元:東京都保健医療局
【そのまま使用OK!】プロテインの広告に使える表現一覧
プロテインの広告を作成する際、どのような表現が適切で効果的なのか迷うことはありませんか?
ここでは、薬機法を守りながら商品の魅力を伝える広告表現を一覧表にまとめました。それぞれの表現がどんな訴求に適しているかも解説していますので、目的に合ったキャッチコピーを選ぶ際の参考にご活用ください!
| No | 広告表現 | 訴求したい効果 |
|---|---|---|
| 1 | カラダづくりを応援する、プロの栄養サポート | 日常的なたんぱく質補給の習慣化を訴求したい時 |
| 2 | ジムでも、オフィスでも。どこでもサッとプロテイン | 外出先でも手軽に使える便利さを伝えたい時 |
| 3 | 頑張るあなたに、続けやすい美味しさを | 味の良さで訴求する時 |
| 4 | 高コスパで毎日飲める | コストパフォーマンスの良さを訴求する時 |
| 5 | 女性に嬉しいソイプロテイン | 成分の良さで訴求する時 |

ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。
薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのプロテインならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。
弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。
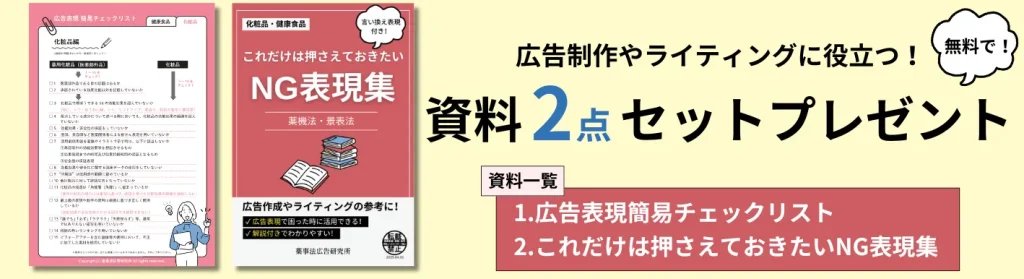
よくあるNG表現
ここからは、食品であるプロテインの広告表現において、薬機法に抵触するNG表現をご紹介します。
プロテインといえば筋肉増強、ダイエット、というイメージもありますが、そのイメージをそのまま表現してしまうことでNG表現になってしまうことも多々あります。
言い換え表現とともに、なぜNGとなってしまうのかも一緒に説明していきます。
【NG表現①】「飲むだけで筋肉量が驚くほど増加!」
「飲むだけで筋肉量が驚くほど増加!」は医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。
食品であるプロテインで言えるのは、摂取による栄養補給までであり、身体へ何らかの効果があるかのような標ぼうはできません。しかも「驚くほど」増えるとなると虚偽誇大な表現にもなります。そのため、プロテインを摂取するだけで筋肉が驚くほど増えるかのような標ぼうはNGとなります。
筋肉量が増加するのは、あくまでプロテインを摂取した人が自分でトレーニングを行うことによるものであるというロジックが必要です。
言い換え表現:「追い込むあなたにプロテイン!」
【NG表現②】「短期間でスリムボディ!」
「短期間でスリムボディ!」は、医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。
こちらも①と同様の考え方となりますが、食品であるプロテインで標ぼうできるのは、摂取することによる栄養補給までです。プロテインを飲むだけで痩せるとすると、痩身効果を述べていることになります。これは医薬品的な効果の標ぼうとなるため、NGとなります。
体をスリムにするのは、摂取した人自身のトレーニングや食事制限などの努力によるものでなければいけません。
言い換え表現:「フィットネスのお供に!」
【NG表現③】「関節の痛み対策に!」
「関節の痛み対策に!」は、医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。
「関節」という特定部位への効果の標ぼうに加え、痛みを緩和、予防できるかのような表現は医薬品的な効果の標ぼうとなるため、NGとなります。プロテインで栄養補給しながら運動をし、これからも元気で動ける体に鍛えていく、という流れであれば標ぼう可能となります。
言い換え表現:「ずっと元気で歩みたいあなたを応援!プロテインでタンパク質補給!」
【NG表現④】「プロテインで目指せ健康体!」
「プロテインで目指せ健康体!」は、医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。
一見良さそうに見えるのですが、「プロテインで目指せ健康体」と訴求するということは、健康でない人がプロテインを飲むことで健康体になると述べていることになります。健康でない人を健康にするのは医薬品的な効果の標ぼうとなり、NGとなります。
【もともと健康な人がこれからも健康でいるため】の健康維持をサポートするというものであれば標ぼう可能となります。また、「目指せ」は免罪符にはならず、キャッチ全体で医薬品的な効果の暗示となっていれば不可となります。
言い換え表現:「健康維持のために!」
【NG表現⑤】「-10歳ボディをゲット!」
「-10歳ボディをゲット!」は、老化防止や若返りといった医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。
老化防止、若返りといったアンチエイジングの効果は、④でお伝えした健康維持とは異なります。健康な人でも歳をとるのは自然なことであり、プロテインにそこに逆らえるほどの効果があるとすれば、医薬品的な標ぼうとなってしまいますのでNGです。
「若々しい」「ハリのある」といった、あくまで印象にとどまる文言を使用しつつ、栄養補給や健康維持の役割の範囲内に収める必要があります。
言い換え表現:「めざせあの頃の自分!ボディメイクの合間にプロテイン補給!」
薬機法に違反してしまった場合の罰則
ここまでは、プロテインの広告表現でよくある、薬機法上NGとなる表現をご紹介しました。
万が一プロテインの広告表示において薬機法のルールを逸脱した場合、さまざまな罰則が科される可能性があります。
主な罰則としては「刑事罰」「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」があります。ここでは、その中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」の内容について解説します。
行政指導
「行政指導」は、行政機関が違反状態の是正を命じるものです。主に以下の内容が含まれます。
- 違反広告の表現を訂正するよう命じる「是正命令」
- 違反内容や是正措置に関する報告書の提出要求
また、行政指導が行われるきっかけは様々ですが、主に行政機関による監視活動(パトロール)での発覚、消費者からの苦情に基づく調査が挙げられます。時には同業者からの情報提供による通報で発覚し、指導が入るということもあるようです。
措置命令
「措置命令」は、厚生労働大臣または都道府県知事によって違反者に対して下される命令です。
主に、下記の内容が含まれます。
- 行為の中止命令:違反行為を直ちに中止するよう命令
- 再発防止措置:再発防止のための必要な対策を実施するよう要求
- 公示命令:公衆衛生上の危険を防止するために違反内容を公表
措置命令は「誇大広告の禁止(薬機法第66条第1項)」、そして「承認前の医薬品・医療機器等の広告の禁止(薬機法第68条)」に違反した際に発出されます。
課徴金納付命令
「課徴金納付命令」は、誇大広告等(薬機法第66条第1項)に違反する行為に対して課されます。
課徴金の額は、課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価合計額の 4.5%であり、課徴金が 225万円未満の場合は納付命令は適用されません。
また、課徴金対象期間の計算については、虚偽・誇大広告を行った期間が基本となります。虚偽・誇大広告をやめた日から6ヶ月以内に関連商品の取引が行われた場合は、その期間も対象期間に加算されます。対象期間の上限は最長3年間とされています。
薬機法に違反しないための対策
ここまではプロテインの広告において、薬機法上のNG表現や言い換え例について解説してきました。しかし、世に出回るプロテインやそれに類する製品の数を考えると、これまで紹介した内容ですべてのケースを網羅できているわけではありません。
そこで重要になるのが、薬機法のルールを正しく理解した上で、実際の運用でどのように法を守るかという点です。ここからは応用編として、薬機法上のNG表現を避けるための実践的な方法をいくつかご紹介します。
薬機法に関する社内研修を実施する
一つ目の対策は、「薬機法に関する社内研修を実施する」ことです。
特に化粧品広告を扱う企業では、社員へのコンプライアンス教育の一環として研修を行うことが非常に効果的です。
具体的には、東京都が定期的に開催している「事業者向けコンプライアンス講習会」や、化粧品関連の業界団体が主催するセミナーに参加する方法があります。また、民間企業による薬機法や化粧品広告表現に関するセミナーも数多く開催されています。それらを活用することで、最新の法規制情報や具体的な運用方法を学ぶことができるため、社員教育の一環として取り入れることをおすすめします。
広告作成は2人体制で行う
2人以上のチェック体制を構築することも有効です。一人で作業を進めると、どうしても見落としや予期せぬミスが発生しやすくなります。
広告の表現チェックに限らず、多くの業務でミスを減らす手段としてダブルチェックや複数人による確認が取り入れられているのではないでしょうか。複数名で確認を行うことで、ヒューマンエラーを防ぎ、制作物の完成度を高めることが可能です。
ただし、確認する人数が多すぎると「他の人がミスを見つけるだろう」という心理が働き、責任感が薄れることがあります。そのため、複数人でのチェックを行う場合でも、各自が責任を持って作業に取り組める仕組みを整えることが重要です。
広告チェックサービスを活用する
広告チェックサービスを活用することも選択肢の一つです。
薬機法だけでなく、景品表示法や健康増進法、特定商取引法など、広告出稿時には遵守すべき法律が多岐にわたります。これらすべてを網羅的に確認しながら広告を作成するのは非常に手間がかかります。
社内で対応が難しい場合や広告の出稿数が多い場合には、専門家に外注するのも有効な選択肢です。薬機法チェックサービスを利用すれば、効率的に広告表現を精査でき、訴求内容と法規制の両立を図ることができます。
また、広告だけでなく、メールマガジンや店舗POP、コールセンタースクリプトなど幅広い領域のチェックも依頼できる場合があります。事前に表現可能な範囲を相談し、適切な表現を採用することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
チェックツールの活用
もう一つ、すぐにできる対策としては広告チェックツールの活用もおすすめです。
インターネット上には、広告表現が薬機法に抵触していないかをチェックできるツールがいくつか提供されています。無料で使えるもの、有料で使えるものなどがあり、それぞれに特徴があります。その中から、まずは自社の目的に合ったツールを選ぶことが重要です。
ただし、広告表現が薬機法に違反しているかどうかは、広告全体の印象によって判断される場合があります。そのため、ツールを利用しても、「この言葉を使ったからNG」「この表現を避ければOK」と単純に判断することはできません。
それでも、ツールは初期段階での表現チェックに役立つため、「そもそもプロテインでこういう訴求はできないのに、企画を進めてしまった」という事態を防ぐのに有効です。
まとめ
この記事では、プロテインの広告における薬機法に基づく考え方について、いくつかのポイントに絞って解説しました。最後に、この記事の内容をまとめます。
- プロテインは「食品」
- 薬機法上、プロテインは食品だから、医薬品みたいな効果は言えない
- 医薬品的な効果効能や特定部位への効き目を謳う表現はNG
- プロテインにできるのは「栄養補給」
- 痩せる、筋肉がつくなどの効果は医薬品的な効果なのでNG
- 「栄養補給によるトレーニングや運動のサポート」や「味の良さ」「コスパの良さ」などで訴求を
今回は薬機法に基づいてお伝えしましたが、プロテインの広告では他に景品表示法、健康増進法といった法律にもルールが存在します。すべてを一度に理解することは難しいことですが、法を守ることは、消費者の信頼を得ることや、守ることにもつながります。
ルールを遵守しながら、商品の価値を最大限に伝える広告を目指しましょう!
この記事から学んでおきたい関連知識



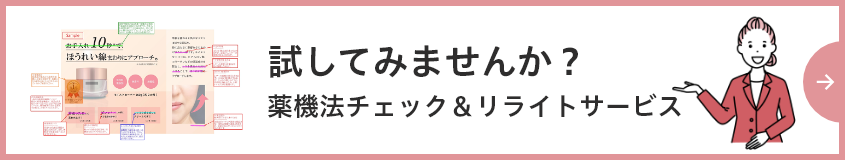


プロテインを扱う広告や販促を行う際、薬機法を意識しなければならないことは皆さまご存じかと思います。
薬機法では、医薬品でないものに対して「医薬品と誤解される可能性のある表現」を表示することに厳しい制限を設けています。適切な広告表現を選ばなければ、意図せず違法となり、信頼を失うリスクがあるのです。
本記事では、プロテインの広告で注意すべきポイントをわかりやすく解説するとともに、そのまま使える表現の実例、よくあるNG表現も複数ご紹介します。
ルールを守りながら、商品の魅力をしっかりアピールする方法を学びましょう!
試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス >