「糖尿病が治る」などと虚偽誇大広告の疑い、医療機器会社代表ら逮捕
「糖尿病が治る」などと本来は認められていない効能をうたって医療機器の宣伝をしたとして、大阪府警は12日、医療機器製造会社「インプレッション」(兵庫県尼崎市)代表の小島雄一容疑者(57)=大阪市北区=や同社幹部ら5人を医薬品医療機器法違反(虚偽誇大広告の禁止)容疑で逮捕したと発表した。認否は明らかにしていない。
生活環境課によると、医療機器は同社が販売する家庭用電位治療器「インプレックスIAS30000R」。体に電流を送ることで、頭痛や肩こり、不眠症や慢性便秘の緩和に効くとされている。
5人の逮捕容疑は、共謀して2022年7月~23年9月、大阪府池田市のスーパーで開かれた同商品の無料体験会で、「血液の循環を良くする」「糖尿病が治る」などと本来は認められていない効能をうたったポスターなどを掲示し、50~80代の女性客4人に対して虚偽・誇大な広告をしたというもの。
会場では同期間中に53台が計約4800万円で販売されたという。
参照元:朝日新聞(2025年2月12日より)
虚偽・誇大な広告が問題だった
この件に関して、主な問題点は以下です。
- 虚偽・誇大広告による薬機法違反
医薬品や医療機器に関する広告は、薬機法により厳しく規制されています。
許可された範囲を超えた効能・効果を謳うことは、消費者に誤解を与え、健康被害につながる可能性もあるため、厳しく取り締まられています。
今回のケースでは、「血液の循環を良くする」「糖尿病が治る」といった効能・効果、性能に関する虚偽・誇大な標ぼうを行ったことで、消費者を誤認させる行為となり、薬機法に抵触しました。
誇大広告にはどのような問題があるのか
今回のニュースをもとに、誇大広告が引き起こす具体的な問題について解説します。
- 消費者の誤解を招く
「糖尿病が治る」という表現を見た消費者は、「この機器を使えば病院に行かなくても完治する」と誤解し、適切な医療を受ける機会を失う可能性があります。これは健康被害につながるリスクがあり、社会的に大きな問題となります。 - 承認されておらず、根拠も不明
薬機法に基づく承認、もしくは規定による認証を受けていない医薬品や医療機器等は、その承認前にその名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならないとされています。本件の電位治療器は、肩こりや不眠症などの緩和が認められているものの、糖尿病の治療効果について承認を得ておらず、また当商品が合理的根拠を有するかも不明です。 - 事業者の信頼が失われる
違法な誇大広告が発覚すると、企業の信用が大きく損なわれます。特に医療機器業界では、信頼が非常に重要であり、一度の違反が経営に致命的なダメージを与える可能性があります。
事業者が今後注意すべきポイント
この問題を踏まえ、事業者は以下の点に注意する必要があります。
①広告表現の厳格な管理
医療機器の広告で効果を謳う際には、医療機器のクラスに応じて届出・認証・承認に沿った内容のみに留める必要があります。
例えば、「頭痛や肩こり(に効く)」という表現は、許可された範囲内の広告ですが、「血液の循環が良くなる」「糖尿病が治る」といった標ぼうは、届出・認証・承認のいずれかがされない限りできません。。
また、次のような表現も違法となる可能性があるため注意が必要です。
✅ 「絶対に治る」「誰でも効果を実感できる」などの断定的な表現
✅ 「医学的に証明されています」と根拠のないデータを示す
✅ 「○○医師も推奨」等、医薬関係者による推薦
広告を作成する際は、社内でチェック体制を設け、法的に問題のない表現になっているか確認することが重要です。
②販売活動の透明性を確保する
広告だけでなく、実際の販売活動においても、消費者が誤解しないように説明することが大切です。
例えば、店舗やイベントで医療機器を販売する場合、次のようなルールを徹底しましょう。
✅ 商品の効能・効果について、届出・認証・承認のいずれかがされた内容のみ説明する
✅ 「個人差がある」「必ず効果があるわけではない」といった注意喚起を行う
✅ 消費者が落ち着いて判断できるよう、即決購入を促さない
特に高額な医療機器の場合、消費者が冷静に検討できる時間を確保することが、トラブル回避につながります。
なお、「個人差がある」「必ず効果があるわけではない」といった注意喚起をすれば何を言っても良いということではありません。免罪符にはならないことを認識しておきましょう。
また、従業員向けの研修を実施し、販売時の適切な説明方法を指導することも重要です。
まとめ
今回の事件では、「高齢者向け販売」や「体験会」といった販売手法が問題なのではなく、「虚偽・誇大広告」を行ったことが法令違反となり、事業者が逮捕される事態に発展しました。
誇大広告は短期的な売上向上にはつながるかもしれませんが、発覚すれば企業の存続すら危うくなるリスクがあります。そのため、事業者は、法令を遵守し、科学的根拠に基づいた適正な広告活動を行うことが求められます。
適切な広告表現や販売方法を守ることで、消費者の信頼を得るだけでなく、企業としてのブランド価値を高めることにもつながります。
このニュースから学んでおきたい知識



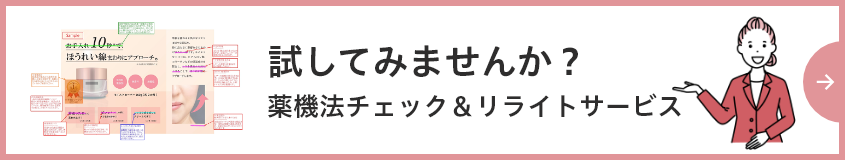


兵庫県尼崎市に本社を置く医療機器製造会社「インプレッション」の代表と幹部ら5人が、医薬品医療機器法(薬機法)違反の疑いで逮捕されました。
同社が販売する家庭用電位治療器「インプレックスIAS30000R」は、頭痛や肩こり、不眠症、慢性便秘の緩和が認められているものの、逮捕された人物らは「血液の循環を良くする」「糖尿病が治る」といった、本来認められていない効能を宣伝。
大阪府池田市のスーパーで開催された無料体験会にて、虚偽・誇大な広告を行い、50~80代の女性客4人に対して販売活動を行ったとされています。この体験会では、約1年2カ月の間に53台、総額約4800万円分の機器が販売されていました。
本記事では、この事件の問題点や、今後事業者が注意すべきポイントについて解説します。
【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >