中部経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者である株式会社SEED(本店所在地:東京都墨田区)(注)(以下「SEED」といいます。)に対し、令和7年3月3日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、停止するよう命じました。
(注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。
あわせて、中部経済産業局は、SEEDに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、中部経済産業局は、SEEDの代表取締役である坂本 周三(さかもと しゅうぞう)に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、前記取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。
参照元:消費者庁HP(2025年3月4日より)
Contents
特定商取引法とは
特定商取引法(特商法) は、消費者トラブルを防ぎ、公正な取引を確保するために制定された法律です。この法律は、特にトラブルが発生しやすい販売形態に対して、事業者に一定のルールを課しています。
特定商取引法が規制する主な取引
特商法では、以下のような取引形態が規制の対象となります。
- 訪問販売(自宅や職場への訪問による勧誘)
- 通信販売(インターネットやカタログ販売)
- 電話勧誘販売(営業電話による販売)
- 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
- 特定継続的役務提供(エステ・語学教室などの長期契約型サービス)
- 業務提供誘引販売取引(内職商法など、仕事を提供するとして金銭を支払わせる手法
今回の行政処分の対象となったのは、④連鎖販売取引 に関する違反です。
連鎖販売取引とは、会員が新たな会員を勧誘し、紹介者に報酬が支払われる仕組みを持つビジネスモデルで、一般的には「マルチ商法」として知られています。
この仕組み自体は違法ではありませんが、違法な勧誘方法や誇大広告、不適切な契約手続き などが問題となるケースが多く、特商法で厳しく規制されています。
連鎖販売業者とは
連鎖販売業者とは、「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」とも呼ばれる販売形態を採用している企業のことです。
これは、商品の販売だけでなく、新たな販売員(会員)を勧誘し、その会員がさらに他の人を勧誘することで販売網を広げていくビジネスモデルです。
- 会員登録:最初に商品を購入し、会員として登録。
- 販売・勧誘:商品を販売するだけでなく、新たな会員を勧誘。
- 報酬の獲得:自分が直接販売した利益に加え、自分が勧誘した会員(下位会員)の売上の一部も報酬として受け取れる。
日本では、「特定商取引法」によって連鎖販売業が規制されており、誇大広告や強引な勧誘が禁止されています。違反すると業務停止命令や罰則が科されることもあります。
- 合法なものと違法なものがある:適切に運営されている企業もありますが、違法なねずみ講と混同されることも。
- 収益が安定しにくい:成功するためには継続的な勧誘と販売が必要。
- 社会的イメージ:悪質な業者の影響でネガティブな印象を持たれやすい。
連鎖販売業を利用する際は、契約内容やビジネスモデルを慎重に確認することが重要です。
何が問題なのか?
今回の行政処分は、特定商取引法に基づく厳しい措置であり、特に連鎖販売取引(マルチ商法)に関する違反 が問題視されました。
違法な勧誘手法は、消費者にとって大きな被害をもたらすため、行政処分の対象となります。
- 氏名・勧誘目的の不明示(特商法第33条の2違反)
・勧誘時にSEEDの社名を名乗らず、「ボウリングしませんか?」「社会人サークルの集まりです」 などと誘い、事業目的を隠していた。 - 勧誘目的を告げずに誘引し、公衆の出入りしない場所で勧誘(特商法第34条第4項違反)
・勧誘目的を告げずにLINE通話などで特定の場所に呼び出し、その後、SEEDの事務所などで勧誘を行っていた。 - 迷惑勧誘(特商法第38条第1項第3号違反)
・断った相手に対し、「続ければ必ずリターンがある」「絶対にやったほうがいい」などと深夜まで長時間勧誘を続けた。
・例えば、午後11時30分から午前3時まで、約3時間半も契約を迫るケースがあった。
消費者保護の観点からの問題点
連鎖販売取引は、適切に運営されていれば合法ですが、違法な勧誘や契約方法が横行すると、以下のような消費者被害が発生します。
- 高額な初期費用や在庫の購入を強要される
- 勧誘によって人間関係が悪化する
- 実際には収益を得られず、借金を抱えるケースがある
こうしたトラブルを防ぐために、特商法は厳格なルールを定めています。
今回のケースでSEEDは、会員勧誘の際に会社名や目的を隠したり、迷惑な長時間勧誘を行ったことが問題視され、18か月間の業務停止命令 やコンプライアンス強化の指示 が下されました。
さらに、代表取締役の坂本周三氏に対しても、以下の業務が18か月間(2025年3月4日~2026年9月3日) 禁止されました。
これは、SEEDの違反行為に経営者として責任があると判断されたためです。
これは、連鎖販売取引において、消費者保護を無視した違法な勧誘 が厳しく取り締まられることを示しています。
事業者は、適正な勧誘や法令遵守の重要性を改めて認識する必要があるでしょう。
コンプライアンス違反のリスク
企業にとって、特商法違反による行政処分は、以下のような深刻な影響をもたらします。
特商法違反は一度処分を受けると、企業の存続そのものが危ぶまれるケースもあり、コンプライアンス(法令遵守)の徹底が不可欠です。
事業者が意識しておくべき点
事業者として適正な取引を行うために、特に以下のポイントを意識することが重要です。
適正な勧誘・契約を徹底する
連鎖販売取引では、新規会員を勧誘する際に以下のルールを守る必要があります。
法令遵守のための対策を講じる
企業として特商法を遵守するためには、社内の仕組みを整える必要があります。
コンプライアンス体制の強化の重要性
今回のSEEDのケースのように、法令違反による行政処分は、企業にとって致命的なダメージを与えます。そのため、事業者は日頃からコンプライアンス意識を高め、適正なビジネスを行う仕組みを作ることが不可欠です。
特に、以下のポイントを強化することで、特商法違反のリスクを低減できます。
企業が適正な販売活動を行い、消費者からの信頼を獲得することが、長期的な事業の安定につながります。
まとめ
特定商取引法は、消費者を守るために定められた法律であり、事業者はこの法律を正しく理解し、遵守することが求められます。
違反すると行政処分 や 企業の信用低下 だけでなく、最悪の場合、事業の継続が難しくなることもあります。
今回のSEEDに対する行政処分は、特商法違反がいかに重大な問題であるかを示しています。
事業者としては、適正な取引の実施・コンプライアンス体制の構築・従業員教育の強化 を徹底し、消費者に信頼されるビジネスを行うことが不可欠です。
このニュースから学んでおきたい知識



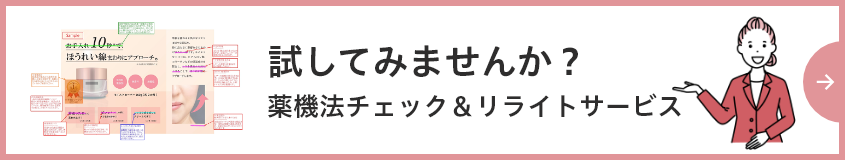


2025年3月3日、中部経済産業局は、化粧品や健康食品を販売する株式会社SEED(東京都墨田区)に対し、特定商取引法に基づく行政処分を行いました。
連鎖販売取引に関する業務が18か月間停止 されるという厳しい措置が取られ、代表取締役にも業務禁止命令が下されました。
加えて、SEEDに対しては、再発防止策の実施 とコンプライアンス体制の構築 を指示。
さらに、SEEDの代表取締役である坂本周三氏には、同じ連鎖販売取引に関する業務を新たに開始することの禁止命令 も下されました。これは、新たな法人を設立したり、他の会社の役員として同様の業務を行うことも含まれます。
今回の処分は、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局が実施したもので、特定商取引法違反に対する厳しい措置であることがわかります。
このニュースを受けて、「特定商取引法とは?」「連鎖販売取引とは?」「今回の処分の問題点は?」「事業者として気をつけるべきことは?」といった点について、詳しく解説していきます。
【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >