医療法人社団がステマ、“星5つ”の口コミ条件に治療費5000円値引く…消費者庁が措置命令
個人の感想を装って宣伝を行うステルスマーケティング(ステマ)をしたとして、消費者庁は18日、医療法人社団「スマイルスクエア」(東京都世田谷区)に対し、景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出したと発表した。命令は17日付。
消費者庁 発表によると、同社団は昨年5月から9月まで、経営する歯科医院「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」(世田谷区)で患者9人に対し、グーグルマップの口コミに「星五つ」の高評価や感想を書いてもらう条件で治療費5000円の値引きなどを行っていたという。
同庁が調査した結果、これらの口コミは歯科医院側が表示内容の決定に関与していたと判断し、ステマによる不当表示と認定した。
参照元:讀賣新聞オンライン(2025年3月18日より)
Contents [非表示]
ステルスマーケティングの定義
ステルスマーケティング、略して「ステマ」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことを「ステルスマーケティング」と言い、個人の感想やレビューに見せかけて、実は企業が意図的に関与している宣伝行為を指します。
たとえば、SNSの投稿や口コミサイトのレビュー、ブログ記事などが、企業からの依頼や金銭的な報酬を受け取って作成されたものであるにもかかわらず、それが明示されていない場合、それはステマに該当します。
2023年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法により規制されることになりました。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守る法律です。
なぜ今ステマが増えているのか
インターネットやSNSの普及により、個人が情報を発信する機会が急速に増えています。
企業としても、従来のテレビCMや新聞広告よりも、一般ユーザーのリアルな声(に見える情報)の方が「信頼されやすい」「通常の広告よりもコストをかけずに気軽に依頼できるから利益を生みやすい」という側面に注目し、マーケティング手法としてSNSや口コミを活用することが一般化するようになりました。
しかし、その裏で「広告と気づかれずに宣伝する」手法が問題視されるようになり、消費者庁もステマへの対応を強化しています。
「消費者を誤認させる」という点で共通するのが、昔から存在する「サクラ」です。
ステマは広告であることを隠して宣伝する行為、サクラは実在の顧客を装って人気や信頼を演出する行為であり、手法はやや異なりますが、景品表示法の観点から、消費者に誤認を与える可能性のある表示についてはどちらも厳しくチェックされるようになっています。
ステマのなにが問題点なのか
ステルスマーケティング(ステマ)は、見た目は自然な口コミやレビューに見えても、実際には企業が関与している「隠れた広告」です。
このような手法が問題となるのは、単に「不誠実だから」という道徳的な理由だけではありません。消費者の適正な判断を妨げ、法令に違反するリスクがあるためです。
①消費者が広告だと気づきにくい
消費者は、第三者による口コミやレビューを「広告よりも信頼できる情報」として受け取ります。これは、発信者が広告主と無関係な立場であると信じているからです。
しかし実際は、事業者が関与しているにもかかわらず、それが明記されていない場合、消費者は広告だと気づかずに判断してしまい、正しい選択ができなくなります。
今回のケースでは、歯科医院が患者9人に対してGoogle Mapの口コミに「星5つ」の高評価や感想を書いてもらうという条件で治療費5000円の値引きなどを行っていました。
その口コミを見て「実際に治療を受けた患者の満足度が高いからこの歯科医院を選ぼう」と考えた人が、報酬目的で書かれていた口コミだと後から知った場合、その判断自体が騙されていたことになると言えます。
②景品表示法に違反する可能性がある
景品表示法は、消費者に誤認を与えるような広告表示を禁じています。
特に問題となるのは以下の点です。
- 優良誤認表示:実際よりも著しく優れていると誤認させる表示(不当表示)
- 有利誤認表示:実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示
- その他の不当表示
今回のケースでは「広告ではない」ように装った表示でありながら、企業が関与したことを隠しているため、「表示自体の誤認」(その他の不当表示)に該当します。
本来、広告であるなら「PR(大文字)」「広告」など明示することが必要ですが、それがなされていない場合、不当表示として違法とされる可能性が高くなります。
③信用を失う・炎上の可能性がある
法的なリスクを受ける以上に、企業にとって深刻なのは信頼の喪失です。
世間に公表されると、消費者の間で「この会社は信用できない」「評価を金で買っていたのか」といった反感が広まり、SNSや口コミサイトで炎上することも少なくありません。
一度失った信頼を取り戻すには非常に長い時間とコストがかかるため、短期的な集客効果を狙ったステマは、長期的には企業価値を損なう結果を招くと言えます。
ステマの2つの種類
ステマは大きく分けて2種類あります。
発信者が誰なのか、企業がどう関わっているかによってその問題点や法律上のリスクが異なります。
①利益提供秘匿型
企業が報酬や金銭などの利益を第三者(インフルエンサー、顧客など)に提供して広告を依頼したにもかかわらず、広告であることを表示せずに投稿する(させる)ケースです。
今回のケースは「利益提供秘匿型ステマ(利益提供秘匿表示)」に該当します。
2023年10月に施行された消費者庁のガイドラインでは、これを「表示主体が事業者であるにもかかわらず、それを隠して表示された場合」と位置づけ、景品表示法上の不当表示(優良誤認)として違法と明示しました。
スマイルスクエアの事例
・治療費5,000円の値引き(=経済的利益)または5,000円分のギフトカードを患者に提供していた
・対価を得て書かれたにもかかわらず、口コミにはその事実が一切表示されていない
・投稿は「広告」とみなされるにもかかわらず、「広告」等の明示がなかった
これは消費者庁が問題視する「利益提供秘匿型」の典型といえます。
②なりすまし型
企業やその関係者が、一般の消費者を装って(=なりすまして)投稿や発信を行うタイプのステマです。
特徴
・投稿者が実在の消費者ではない(例:企業の社員や関係者)
・本来は企業側の発信なのに、それを隠して「第三者の意見」と装う
・口コミサイトやSNS、レビュー欄で多く見られる
事例
・店舗スタッフが「一般客」を装って高評価レビューを投稿
・自社社員が匿名で「この商品、最高です!」とSNSで拡散
・架空アカウントを大量に作り、“人気商品”を演出する
措置命令のリスク
ステマ広告とみなされた場合、消費者庁から「措置命令」が出されることがあります。
措置命令は行政処分であり、企業イメージに大きな打撃を与えるとともに、他社や消費者からの信頼を一気に失う要因となります。
措置命令に従わない事業者は、2年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、もしくはこれらの併科となる可能性があります。
今回のケースにおいて口コミを投稿した患者さんや、広告を依頼された第三者、インフルエンサーなどに法的なペナルティが科されることはありません。
しかし、SNSなど情報が瞬時に拡散されるため、フォロワーの減少や炎上、イメージ低下といった社会的制裁を受けるリスクは十分に考えられる為、注意が必要です。
事業者が意識すべき点とステマ防止のための対策
ステマをめぐる法規制が強化される中で、企業や店舗、医療機関など、消費者向けに情報を発信するすべての事業者が注意を払う必要があります。
特に、インフルエンサーの活用や口コミ投稿の依頼といった「第三者による情報発信」が当たり前になった現代では、意図せずして違法なステマをしてしまうリスクも高まっています。
事業者がステマを防ぐために意識すべきポイントと、実際の対策を詳しくご紹介します。
①「広告であること」を必ず明示する
ステマと判断されるかどうかは、消費者がその表示を広告と認識できるかどうかがポイントになります。
インフルエンサーや顧客、モニターに投稿を依頼する場合は、報酬・割引・商品提供などの見返りがある場合、必ず「PR(大文字)」「広告」「タイアップ」「提供:〇〇」などの明示が必要です。
- SNS投稿:本文冒頭に【PR(大文字)】【広告】などを明記する
- ブログ:タイトルや記事の上部に「本記事は〇〇社から依頼を受けて執筆しています」と記載
- 動画:サムネイルや冒頭で「プロモーションを含みます」などの表記
②投稿者の自主性を尊重する(内容の指示は禁止)
口コミやレビューを依頼する際、「ポジティブな内容を書いてください」「星5でお願いします」といった指示はNGです。
投稿内容が企業の指示に基づく場合、それは広告表示とみなされ、ステマと判断されるリスクが高くなります。
「実際に体験した範囲で、自由な感想をお願いします」
「投稿は任意です。無理に高評価を書かなくても構いません」
③ガイドライン・マニュアルの整備と徹底
広告制作・広報活動に関わる社員や店舗スタッフ、または外部のマーケティング担当者、インフルエンサー向けに、「ステマ防止のための社内ルール」「べからず集」などを整備しておくことが重要です。
- インフルエンサーや顧客に情報発信を依頼する際のルール
- PR表記の具体例
- 違反した場合の対応方針
- 社外スタッフ・代理店との契約書面への明記
④消費者庁のガイドラインを参考にする
2023年10月、消費者庁はステマを景品表示法の「不当表示」として明確に取り締まる方針を打ち出し、「ステマに関する表示の明確化に関するガイドライン」を公開しました。
この資料は、どのような行為が違反になるのか、どのように広告表示をすればよいのかを具体的に示しています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
企業としては、このガイドラインに基づいた運用体制を構築することが、法令遵守と信頼確保の鍵になると言えます。
まとめ
ステマの本質的な問題は、「広告であることを隠して消費者を操作する」ことにあります。
逆に言えば、透明性を持って情報を発信し、消費者に誤解を与えない姿勢を徹底すれば、ステマと疑われるリスクは大幅に下げられます。
「短期的な集客効果」よりも、「長期的な信用と信頼」が企業の価値を高めます。
その意識を全社内で共有することが、最も有効なステマ対策と言えるでしょう。
このニュースから学んでおきたい知識



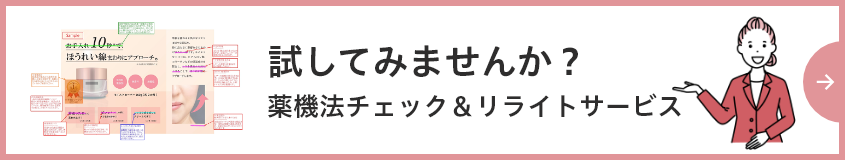


2025年3月18日、消費者庁が東京都世田谷区の医療法人「スマイルスクエア」に対し、景品表示法違反で措置命令を出したというニュースが報じられました。
患者にGoogle Mapでの高評価の口コミ投稿を促す代わりに治療費を割引していたことが、広告であることを隠した不当表示=ステルスマーケティング(ステマ)と認定されたのです。
本記事では、この事例をもとに、ステマとは何か、なぜ問題なのか、そして企業がどのような点に注意すべきかをわかりやすく解説します。
【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する >