Contents
- 1 製造方法関係
- 2 効能効果、性能及び安全性関係
- 2.1 承認された効能効果等以外の効能効果等について
- 2.2 複数の効能効果を有する医薬品等の広告について
- 2.3 効能効果等⼜は安全性の保証表現について
- 2.4 医薬品等の歴史的な表現について
- 2.5 臨床データ等の例⽰について
- 2.6 図画、写真等について
- 2.7 使用体験談等について
- 2.8 疾病部分の炎症等が消える場合の表現について
- 2.9 副作用等の表現について
- 2.10 医薬品等の広告における「すぐれたききめ」、「よくききます。」の表現について
- 2.11 (1) 効能効果等の発現程度について
- 2.12 (2) 速効性に関する表現について
- 2.13 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限
- 2.14 医療用医薬品について
- 2.15 医薬関係者の推せんについて
- 2.16 懸賞、賞品等による広告の制限
製造方法関係
医薬品等の製造方法について、実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識をさせるおそれのある表現をしてはいけません。
製造方法等の優秀性について
広告で製造方法を紹介する場合、「最高の技術」や「最先端の製造方法」などの最大級の表現や、「近代科学の粋を集めた製造方法」、「理想的な製造方法」、「家伝の秘法による作成」などの表現は、実際の優秀性について誤解を与える恐れがあるため、使用しないようにしましょう。
ただし、製造部門や品質管理部門、研究部門についての広告は、事実に基づいていて、製造方法の優秀さについて誤解を与えない場合には問題ありません。
特許について
特許について虚偽の広告を行うことは禁止されています。ただし、事実に基づいた特許の広告は、規定に従って正しく扱うことができます。
⇒特許について
研究について
製造業者が「研究」を行うことは当然ですが、その製品に関連する研究内容を広告で述べる際には、事実を正確に伝え、誇張しないようにすることが重要です。

医薬品や健康関連製品の広告において、製造方法やその優秀性を過大に表現してはいけません。「最高の技術」や「家伝の秘法」といった表現は誤解を招く可能性があります。
特許や研究についても、事実に基づいた正確な情報提供が必要です。誇張表現を避け、消費者に正しい認識を持たせることが重要です。
効能効果、性能及び安全性関係
医薬品やその他の承認が必要な製品について、その効能効果や性能(以下「効能効果等」)を広告や説明する場合、明示的であれ暗示的であれ、承認された効能効果等の範囲を超えて表現してはなりません。 つまり、製品が正式に認められた範囲内でしか、その効果や性能を伝えてはいけません。例えば、医薬品として認可された治療効果や性能が特定の症状に対するものである場合、それ以外の効果を広告することは禁止されています。このルールを守ることで、消費者に正確で信頼できる情報を提供し、誤解を避けることができます。 これらのポイントを理解して、適切に広告や説明を行うことが重要です。 医薬品などが承認されている効能効果以外に、実際に効能効果がある場合や、追加申請をすればその効能効果が承認される可能性がある場合でも、未承認の効能効果を広告することは禁止されています。 つまり、たとえ実際に効果があっても、その効果がまだ正式に承認されていない限り、広告や説明にその効果を含めることはできません。 複数の効能効果を持つ医薬品などの広告を行う際には、その中から特定の一つの効能効果だけを広告することは問題ありません。 ①「○○剤」という表現について ②「○○専門薬」等の表現について このように、医薬品等の広告においては、特定の効能効果を適切に表示し、誤解を与えないよう注意が必要です。 医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実であることを保証をするような表現をしないものとする。 例えば、胃腸薬の広告で「胃弱」「胃酸過多」などの適応症を挙げ、それが「根治」「全快する」などと表現することや、「安全性は確認済み」「副作用の心配はない」などの表現を使い、どのような要因や条件に関係なく、効能効果や安全性が確実であることを保証するような表現は認められません。 この規定は、患者の性別や年齢、疾病の要因に関係なく、医薬品等が確実に効果を発揮し、安全であることを示すような表現を避けることで、消費者に誤解を与えないようにする趣旨です。 これにより、製品の効果や安全性について過剰に保証することなく、正確で信頼性のある情報を提供することが求められます。 特定の医薬品に関係なく、その企業の歴史を示す事実として「創業○○年」などと広告することは問題ありません。 つまり、、企業の歴史や創業年数を示すだけであれば、それが特定の医薬品に直接関係していない場合、そのような表現を使用しても差し支えないということです。 このような表現は、企業の信頼性や実績を示すために使用されるものであり、消費者に対して誤解を与える可能性が低いため、認められています。 一般向けの広告において、臨床データや実験結果を示すことは、消費者に対して十分な説明ができず、かえって医薬品などの効能効果や安全性について誤解を与える恐れがあります。そのため、こうしたデータを広告に使用することは避けるべきです。 具体的には、一般消費者が専門的なデータや実験結果を正しく理解するのは難しいため、それらを広告に含めると誤解や不正確な情報が広まる可能性があるということです。したがって、臨床データや実験例の使用を控えることで、消費者に対して適切でわかりやすい情報を提供することが重要です。 使用前後に関わらず、図面や写真などによる表現については、以下のような表現は認められません。 これらの表現は、消費者に対して誤解を与える可能性があるため、使用が禁止されています。これにより、製品の広告が事実に基づいたものであり、正確で信頼できる情報を提供することが求められます。 愛用者の感謝状や感謝の言葉、「私も使っています」といった使用経験や体験談を広告に用いることは、客観的な裏付けにはならず、消費者に対して医薬品などの効能効果や安全性について誤解を与える可能性があるため、避けるべきです。 ただし、以下の場合は問題ありません。 これらの表現においても、過度な表現や保証的な表現を避けるように注意が必要です。 (6)身体への浸透シーン等について これらのポイントを守ることで、消費者に対して正確で信頼性のある情報を提供し、誤解を避けることができます。 テレビ広告やウェブサイトなどで使用する模式図やアニメーションについては、炎症などが消える様子を表現する際に、効能効果を保証するような表現にならないように注意する必要があります。 つまり、視覚的な表現があたかもその製品が確実に効果を発揮するかのように見せることは避けるべきです。消費者に誤解を与えないためにも、製品の効果を過度に保証するような描写は控えることが重要です。 「副作用が少ない」「比較的安心して……」「刺激が少ない」などの表現は、安全性について誤解を与える恐れがあるため、使用しないようにしましょう。 ただし、以下の場合は例外として認められます。 これらの表現を使用する際には、他社製品の誹謗広告とならないように注意することが重要です。これにより、消費者に正確で信頼性のある情報を提供し、誤解を避けることができます。 「すぐれたききめ」や「よくききます」といった表現は、キャッチフレーズなどの強調表現として使用することは認められません。強調表現とは、以下のような表現を行った場合を指します。 人の注意を引くように工夫した印象的な宣伝文句を使用すること。 例:「よくきく○○○」、「○○○はよくきく」 他の文字と比較して大きくする、色を濃く(または淡く)する、色を異なるものにする、文字の上に点を打つなど。 大きな声で発音する、一音ずつ切って発音する、「よーく」と強く伸ばすなど。 「すぐれた」と「よくききます」を重ねて表現すること。 これらの強調表現を避けることで、消費者に対して誇大な効果を保証するような誤解を与えないようにすることが重要です。これにより、製品の広告が正確で信頼性のあるものとなります。 医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。 医薬品などの速効性や持続性についての表現は、医学や薬学上認められている範囲を超えてはなりません。例えば、「すぐ効く。」「飲めばききめが三日は続く。」等の表現は、原則として認められません。 単に「速く効く」といった表現の使用は認められません。 ただし、承認された効能効果や用法用量の範囲内で、医学薬学上十分に証明された場合は、以下の状況を除いて「速く効く」などの表現を使用しても差し支えありません。 例1: ヘッドコピーやキャッチフレーズとして使用した場合。 例2: 「早く」という言葉を1回の広告中に原則として2回以上使用した場合。 例: 「液剤だから早く効く」といった表現。 例: 「新幹線の大阪で痛んで京都で治っている」といった表現。 これらの条件を守ることで、消費者に誤解を与えることなく、正確で適切な情報を提供することが求められます。 医薬品等について過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告を行ってはならなりません。 医療用医薬品等の広告の制限 (1) 医療用医薬品とは (2) 特殊疾病用医薬品の広告の制限について このような規制により、一般消費者に対する誤解や不適切な使用を防ぎ、医療用医薬品の安全な使用が確保されます。 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。 医薬品などの推せん広告は、一般消費者に対して大きな影響を与えるため、特定の条件を除き、たとえそれが事実であったとしても不適当とされています。この規定により、消費者が誤解や不信感を抱くことなく、正確な情報に基づいて医薬品を選ぶことができます。 このような広告を避けることで、医薬品の効能効果に対する過剰な期待を防ぎ、消費者に対して信頼性の高い情報を提供することが求められます。 懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。 (1)過剰な懸賞、賞品等による広告の制限 (2) 医薬品を懸賞、賞品として提供する広告の禁止 (3) 容器、被包等と引換えに医薬品を提供する広告の禁止 これらの規定は、消費者に対して過度な期待や誤解を与えることを防ぎ、適切な情報提供を行うために設けられています。 この記事から学んでおきたい関連知識承認された効能効果等以外の効能効果等について
複数の効能効果を有する医薬品等の広告について
「○○剤」という表現は、例えば「解熱鎮痛消炎剤」のように薬効分類として認められており、その分類が適切であれば使用が認められます。しかし、「食欲増進剤」のような表現は認められません。ただし、その表現が効能効果や作用から十分に実証できる場合は、具体的な事例ごと検討されます。
特定の疾患を対象とした表現、例えば「胃腸病の専門薬」や「皮膚病の専門薬」などは、効能効果の範囲や用法容量に関する規定に抵触する可能性があり、医薬品等の広告表現としては適切ではありません。そのため、承認を受けた名称である場合を除いて、こうした表現は認められません。効能効果等⼜は安全性の保証表現について
医薬品等の歴史的な表現について
臨床データ等の例⽰について
図画、写真等について
使用体験談等について
医薬品などが身体に浸透する場面をアニメーションや模型で表現する場合は、効能効果や安全性について虚偽や誇大な表現にならないように十分注意する必要があります。また、アニメーションや写真を用いて作用機序を説明する場合でも、効能効果や安全性を保証するような表現を避けることが重要です。疾病部分の炎症等が消える場合の表現について
副作用等の表現について
医薬品等の広告における「すぐれたききめ」、「よくききます。」の表現について
(1) 効能効果等の発現程度について
(2) 速効性に関する表現について
過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限
医療用医薬品について
医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。
医療用医薬品は、医師または歯科医師が使用するか、これらの者の処方せんや指示によって使用されることを目的として供給される医薬品です。
薬機法第67条の規定により、特殊疾病に使用されることを目的とした医薬品で、医師や歯科医師の指導のもとでなければ使用が危険である医薬品については、一般人を対象とした広告が制限されています。広告の制限を受ける特殊疾病には、「がん」「肉腫」「白血病」が含まれます。医薬関係者の推せんについて
懸賞、賞品等による広告の制限
過剰な懸賞や賞品によって射幸心を煽る方法での医薬品や企業の広告は行ってはいけません。
医薬品を懸賞や賞品として提供する旨の広告は行ってはいけません。ただし、家庭薬を見本として提供する程度であれば、この限りではありません。
医薬品の容器や包装を引換えに医薬品を提供する旨の広告は行ってはいけません。
広告表現でお困りの方へ
「広告審査が通らない」「制作前に文言チェックをしておきたい」「この表現が使えるか相談したい」など、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合せください。簡単な薬機チェックから、本格的なサービス構築まで幅広く対応致します。
サービスのお試しプランもご用意しておりますので、まずは弊社のサービスについてご一読ください。




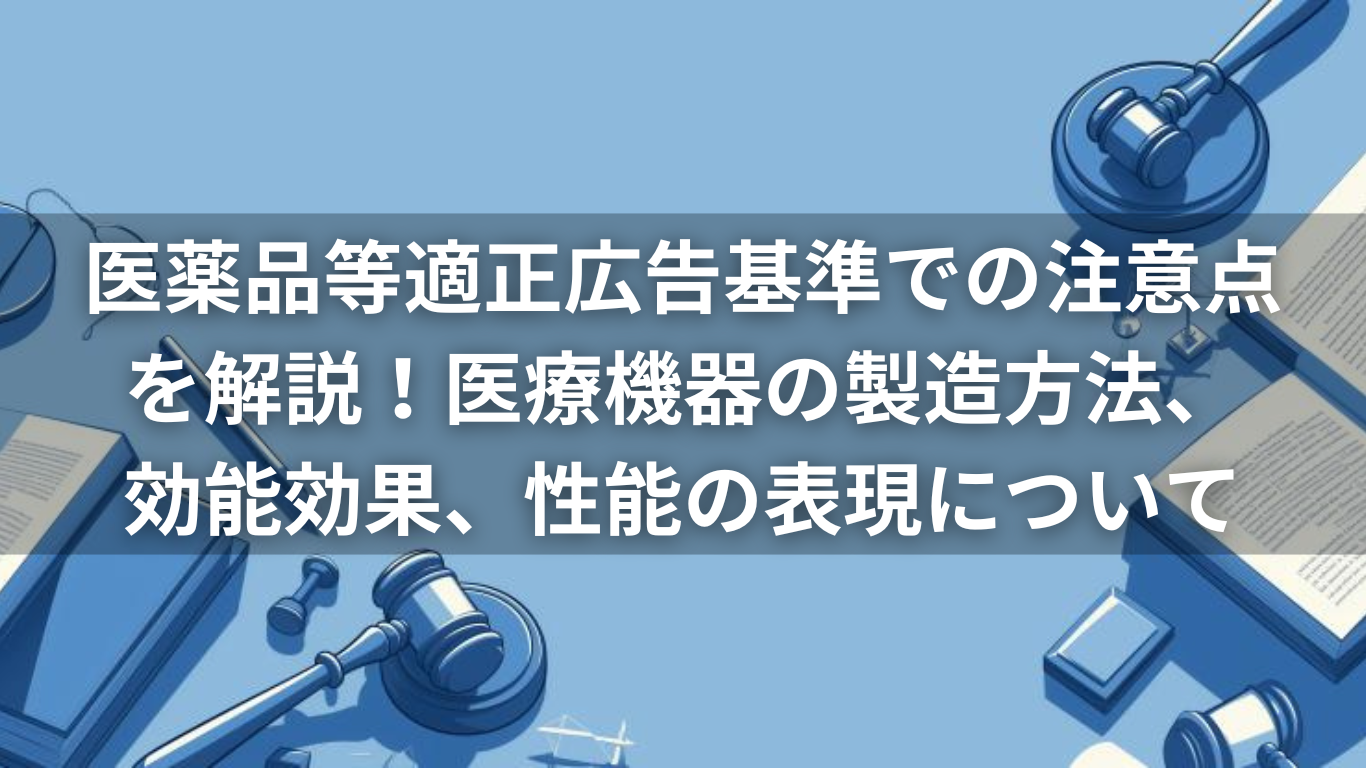
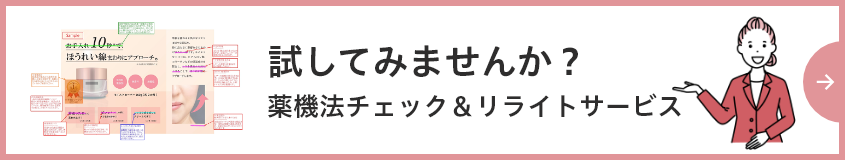
ここでは医薬品等適正広告基準での注意点について解説します。注意点は、「製造方法関係」と「効能効果、性能及び安全性関係」で、今回はこの2点を中心にまとめています。
【1分でアップデート!】薬機法に関する最新情報を取得する >